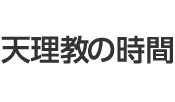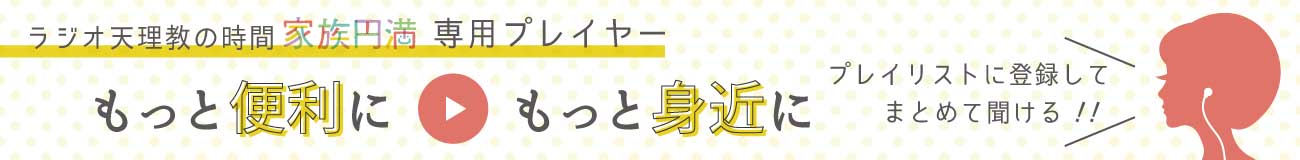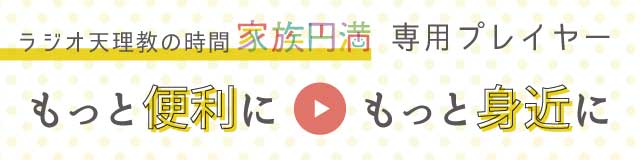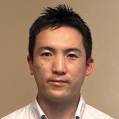第1191回2022年8月13日・14日放送
共に喜び、共に楽しむ
ある人の幸せが、周囲の犠牲の上に成り立っていることがある。それは陽気ぐらしとは言えないのではないか。
共に喜び、共に楽しむ
私たちが個々に幸せを求めるのは、ごく自然なことです。しかし、その幸せが、周囲の人々や環境の犠牲の上に成り立っている場合が往々にして見られます。
たとえば、豊かな暮らしを求めるがゆえの新たな開発によって、自然環境が犠牲になることがあります。そこには、経済的に恩恵を受ける人たちがいる一方で、森林伐採や川の汚染などで見境なく土地が荒らされ、それによって大勢の人たちが影響を受けます。そして、そのような施策が、地球温暖化となって世界全体に跳ね返ってくるという事態を招くのです。
天理教教祖・中山みき様「おやさま」は、
めへ/\にいまさいよくばよき事と
をもふ心ハみなちがうでな(「おふでさき」三 33)
と、いま目の前の出来事に固執して、将来を見通せない私たち人間の心遣いを戒めておられます。
地球環境を考える上では、先を見据える視点を忘れることなく、また、「慎みが世界第一の理」(「おさしづ」M25・1・14)とのお言葉の通り、欲におぼれず、慎みを持ちながら生活したいものです。
現代社会では、政治や経済をはじめ、さまざまな局面で力のある者が優位に立つということが多々あります。しかし、優位に立つ者だけが恵まれるような、他者の犠牲の上に成り立つ幸せは、神様の望まれる真の陽気ぐらしとはほど遠いと言えるでしょう。
お言葉に、
「神が連れて通る陽気と、めん/\勝手の陽気とある。勝手の陽気は通るに通れん。陽気というは、皆んな勇ましてこそ、真の陽気という。めん/\楽しんで、後々の者苦しますようでは、ほんとの陽気とは言えん」(「おさしづ」M30・12・11)
「勝手というものは、めん/\にとってはよいものなれど、皆の中にとっては治まる理にならん」(「おさしづ」M33・11・20)
とあります。
自分たちだけが楽しんで、他の人たちはどうなっても構わないという態度であってはならないということです。陽気ぐらし世界は、相手の立場や考え方にも心を寄せ、共に喜び、共に楽しむという心豊かな姿勢のうちに育まれていくのではないでしょうか。

 HOME
HOME