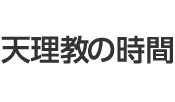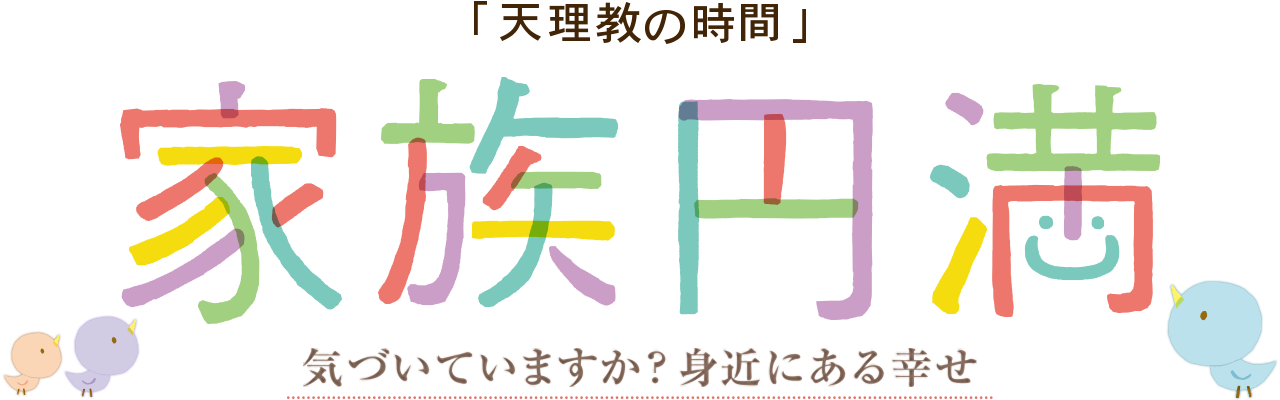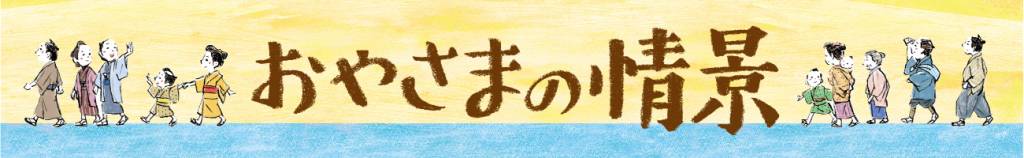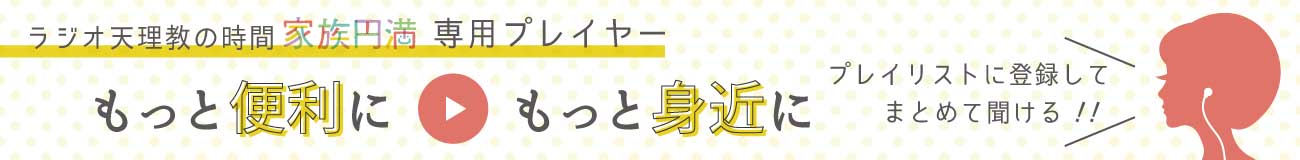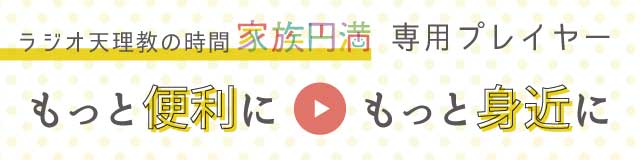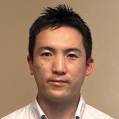「にをいがけ」ってこういう事!?
兵庫県在住 旭 和世
次女が小学一年生になった頃、学校の運動場にあるウンテイが上手になりました。嬉しくて毎日毎日休み時間になると練習をしていたようで、家に帰ってくると、「ママ~手にマメができた~」と嬉しそうに話します。私は、「わ~、そんなマメができるまで練習するなんてすごいね!」と親子で喜んでいました。
数日後、朝の登校時間になってランドセルを背負う時、娘が「腕が痛い…」と言いました。私は筋肉痛だろうと思い、「腕を使い過ぎたんだわ。日にち薬だから大丈夫! いってらっしゃい!」と、不安そうな娘を見送りました。
そしてその日の夕方、娘は学校から帰ってくると、玄関に入るなりランドセルを下ろし、へたり込んでしまったのです。私があわてて駆け寄ると、とてもしんどそうな顔をしていて、額をさわると熱があります。驚いて、とにかくおさづけを取り次がせてもらい、娘を寝かしつけました。
夜になって会長である主人が御用を終えて帰ってきたので、事情を説明すると、すぐにおさづけを取り次いでくれました。
主人が娘に「大丈夫?しんどい?」と声をかけると、「痛い…」と言います。「どこが痛いの?」と聞き返すと、「手が痛い」とのことで、主人がふと見ると、手がグローブのようにパンパンに腫れていたのです。それを見て、これはただ事ではない!となり、急ぎ夜間の救急病院に走りました。
救急病院では、「ここでは見切れないので、明日、大きな病院に行ってください」との事で、翌日市民病院を受診しました。診察の結果は「蜂窩織炎」という病名で、傷口などから細菌が入り、それが炎症を起こして体に回ると重症化する可能性がある、とても怖い感染症だという事を知らされました。
抗生剤の点滴を24時間投与する必要があると言われ、あわてて入院することに。まさか、ウンテイのマメからこんな事態になるなんて思ってもみませんでした。私は気づいてあげられなかったことを後悔し、「本当にごめんね」と娘に謝り、しばらくの入院生活が始まりました。
点滴を開始し、数日間は安静にしていましたが、熱も下がり、腕の腫れも良くなると、すっかり元気になって、そのうち娘は「小児病棟のプレイルームで遊びたい!」と言うほど回復しました。
子供にとれば、ずっと病室にいるのは退屈です。「そうだね!遊びに行こう!」と、二人でプレイルームに行きました。そこにはすでに先客が何人かいて、みんな思い思いに遊んでいます。その中の一人のお母さんと挨拶を交わして中に入り、次女は嬉しそうに遊び始めました。
私はひとしきり遊ぶ我が子を見守っていましたが、ふと、さっきのお母さんが目に留まりました。まるでこの病棟の子供たちをみんな知っているかのように、来る子一人ひとりに声をかけ、色々とお話をしているのです。
このプレイルームの保育士さんかな? いやいや、そんな感じでもない。きっと長い間入院されていて、いろんな子と知り合いになったのかな?ぐらいに思っていました。
そして翌朝、中庭でラジオ体操をするというのでデッキに行くと、またそのお母さんがよその子に声をかけ、面倒を見ている姿がありました。
「わ~すごいな。なんかすごくあったかくて、お道の人みたいに親切なお母さんだな~」と思っていました。
その後、しばらく娘の付き添いを義理の妹に任せ、その後、主人が交代して付き添ってくれていました。すると、しばらくして主人から電話が入りました。
「あのさ~、さっきプレイルームにさやかを連れて行ったら、知らないお母さんが『あら~さやかちゃ~ん!』って話しかけてくれて、うちの子のボサボサの髪の毛を見て気の毒に思ったのか、『髪の毛くくってあげよ~』って言って綺麗に結んでくれてさ~。えらい面倒見のいい方なんやな~と思ってたんだけど、そのお母さんと話してるうちに、同じ市内にある教会の奥さんだってことが分かったんよ! しかも僕の知り合いのお姉さんでさ~、本当にびっくりしたわ~」と、主人は驚いています。
私はその話を聞いて、ビックリしたのはもちろんですが、「やっぱり!あのにをいは、お道のにをいだったんだ!やっぱり教会の奥さんだったんだ!!」と、むしろすごく納得したのです。
そのお母さんは息子さんが大けがをして、緊急で手術をし、ご守護頂きつつあるという事でした。そんな大変な事が起こっているとは思えないほど、とても明るく前向きなお道の女性だったのです。私は本当に感動して、このお母さんに私自身がお道のにをいをかけてもらったな~と思っていました。
「人の子も我子もおなしこゝろもて おふしたてゝよこのみちの人」
という初代真柱様のお言葉があります。
これは、天理養徳院という児童養護施設が設立された時のお言葉です。
「人の子も我が子も、どうか同じ心をもって隔てなく育ててほしい。この道を歩む人々よ」
実に、お道のあたたかい「にをい」がいっぱい詰まったお言葉です。このお母さんは、まさにこのお言葉通りの人だと思いました。そして、そんな素敵な方に巡り合わせて頂けた事を、私は神様に感謝しました。
その後、娘もその息子さんも神様のあざやかなご守護を頂き、元気に退院することが出来ました。それ以来、そのお母さんとなかなか会うチャンスはありませんでしたが、数年経って、お互いの教会が「こども食堂」を開催しているという共通点から、再会することが出来ました。今ではたびたび会う機会があり、いつも本当に元気をもらっています
あの日、娘が蜂窩織炎になっていなければ、こんな風に出逢う事もなかった私たちですが、きっと親神様が「お道のにをいがけというのはこういう事なんだよ」と、私に教えて下さったんだと思います。この出逢いは私にとって、大きなプレゼントになりました。
「人の子も我が子も同じ心をもって…」これは私の永遠のテーマです。教会の御用の時はもちろんの事、こども食堂を開催している時も、いつもこの気持ちを持っていたいと思います。
『教祖伝逸話篇』には、教祖が大人だけでなく、いつ、どこの子供にでも、丁寧な言葉をお使いになったお話が数多く残されています。
教祖の分け隔てない、慈悲深いお心に少しでも近づき、あのお母さんから感じたようなお道のあたたかいぬくもりと「にをい」を、醸し出していけたらなあと思っています。
ひとことの言葉
天理教教祖・中山みき様「おやさま」は、ある日、飯降よしゑさんに、こうお聞かせくださいました。
「よっしゃんえ、女はな、一に愛想と言うてな、何事にも、はいと言うて、明るい返事をするのが、第一やで」(教祖伝逸話篇112「一に愛想」)
日常のちょっとしたことであっても、何事にも「はい」と明るい返事をする。そして「愛想」と言われるように、ただ返事をするだけでなく、顔の表情や身のこなしなど、全身から素直さがにじみ出るような姿が大切でありましょう。
教祖は、別のお言葉においても、
「愛想の理が無けりゃ曇る。曇れば錆る」(M27・7・30)
とお諭しくださいます。一つの「はい」という返事にも心を込め、また、ちょっとした言葉づかいや態度の違いにも目を向けると、世界が違って見え始め、新たな扉が開かれてゆくのです。
教祖が教えられた「みかぐらうた」に、「ひとことはなしハひのきしん」(七下り目 一ッ)とあります。「ひのきしん」とは、神様への感謝を表すご恩報じの行いを指しますが、つまり私たちが発するひとことの言葉が、神様を介してどれほどの大きな意味を持つかもしれない、ということを表しているようにも悟れます。
こんな逸話が残されています。
小西定吉さんは、不治と宣告された胸の病を、教祖にすっきりたすけて頂きました。また、同じ頃、お産の重いほうであった妻のイエさんも、楽々と安産させて頂きました。
お屋敷へお礼に参った定吉さんが、教祖に、「このような嬉しいことはございません。この御恩は、どうして返させて頂けましょうか」と伺うと、教祖は、「人を救けるのやで」と仰せられました。
そこで、「どうしたら、人さんが救かりますか」と再びお尋ねすると、教祖は、「あんたの救かったことを、人さんに真剣に話さして頂くのやで」と仰せ下さいました。(教祖伝逸話篇100「人を救けるのやで」)
自らたすかったことを、自らの言葉で伝えることこそ、神様への大きなご恩報じ、「ひのきしん」となるのです。
(終)

 HOME
HOME