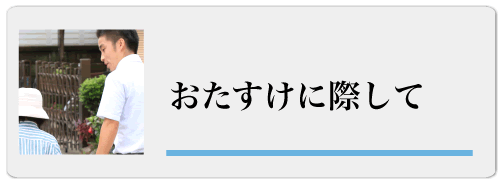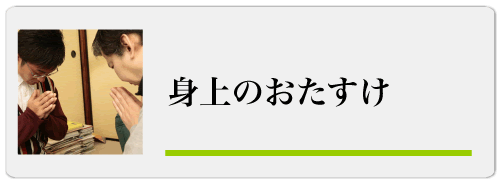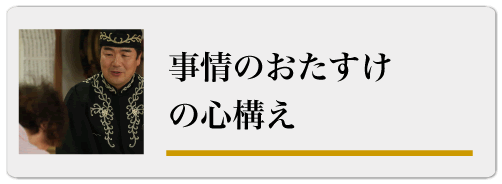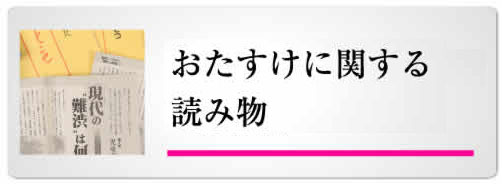身上のおたすけ
おさづけの理拝戴

おさづけの理は、「別席」のお話を9回聞かせていただき、澄みきった心で願い出るところにお渡しくださいます。おさづけの理拝戴時に頂く「おかきさげ」は、ようぼくの“心の定規”となるものですから、繰り返し拝読しましょう。
ようぼくは、病む人に進んでおさづけを取り次がせていただきましょう。親神様は、どうでもたすかってもらいたいと願うようぼくの誠真実と、取り次ぎを受ける者の真実の心定めを受け取って、どんな病気でもおたすけくださいます。
そのためにも、身上を見せてまでも成人をお促しくださる親神様の思召をしっかりお話しし、思召に沿う心に近づいてもらえるよう、自らも精進しなければなりません。
おさづけの理は、たすけ一条を誓う一名一人の真心に、ご存命の教祖から真柱様を通してお渡しくださいます。「国の土産、国の宝」(おさしづ 明治31年12月30日)と教えられる尊いものですが、「道具でもどんな金高い値打でも、心の理が無くば何にもならん」(おさしづ 明治23年7月7日)と示されるように、取り次ぐ人の誠真実が肝心です。
おさづけ取り次ぎ時の心得
 おさづけの取り次ぎは、親神様・教祖が何よりもお喜びくださる尊い人だすけの御用をつとめさせていただくことです。
おさづけの取り次ぎは、親神様・教祖が何よりもお喜びくださる尊い人だすけの御用をつとめさせていただくことです。
親神様の思召は、世界中の人間を一日も早くたすけ上げ、陽気ぐらしをさせたいという「たすけ一条」にあります。ようぼくは、この思召を体し、その自覚を持って、積極的におさづけを取り次がせていただきましょう(おさづけの取り次ぎ方については、『仮席の栞』を参照してください)。そこに、自らも「たすける理がたすかる」結構な姿をお見せいただけます。
ご守護を頂くには、親神様にお受け取りいただく誠真実が何よりも大切ですが、一方で「医者、薬は修理肥」と仰せられ、決して医薬を否定してはおられません。
「たすけ一条」という言葉は、「おふでさき」ではおおむね、親神様のひたすら人間をたすけてやりたい親心を意味していますが、ようぼくがその思召を受けて、人だすけに専心することを指す場合もあります。一般には、ようぼくの心構えとして、後者の意味で使われることが多いようです。
お話を取り次ぐ
 おさづけの取り次ぎに際しては、まず日々頂戴している親神様のご守護のありがたさを納得していただけるようにお話しします。
おさづけの取り次ぎに際しては、まず日々頂戴している親神様のご守護のありがたさを納得していただけるようにお話しします。
その場合、議論をしたり、相手を説き伏せたりするような態度は厳に慎まねばなりません。相手は病気で悩み苦しんでいるのですから、優しくいたわりながら親神様の教えを伝え、心に治めてもらえるよう、真実をもって取り次がせていただきましょう。
病状が重く、意識がないなど、本人が話をできないような場合、家族の人にお話をさせていただきます。そして、家族と共に心定めをし、親神様にお願いをして、病人におさづけを取り次ぎます。重い心の病にかかっている人の場合も同様です。
また、十五歳未満の子どもの病気の場合は、親にお話を取り次ぎ、親と共に心を定め、子どもにおさづけを取り次ぎます。
「小人々々は十五才までは親の心通りの守護と聞かし、十五才以上は皆めんめんの心通りや」(おさしづ 明治21年8月30日)
ひと言お話を
「話一条はたすけの台」と教えられています。ですから、おさづけを取り次ぐだけで、お話をひと言も取り次がないようなことでは十分とはいえません。しかし、「どのようにお話をすればよいのか分からない」という人も少なくないのではないでしょうか。
その方法の一つとして、教祖は「あんたの救かったことを、人さんに真剣に話さして頂くのやで」(『稿本天理教教祖伝逸話篇』100「人を救けるのやで」)と仰せになりました。
また、かつては、「おさづけの理を戴いた者は、『十全の守護』と『八つのほこり』のお話だけでおたすけに出向いていった」とも聞きます。「かしもの・かりものの理」をはじめ、こうした基本教理を学び身につけることは、おたすけに際しても大切なことです。

 HOME
HOME