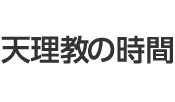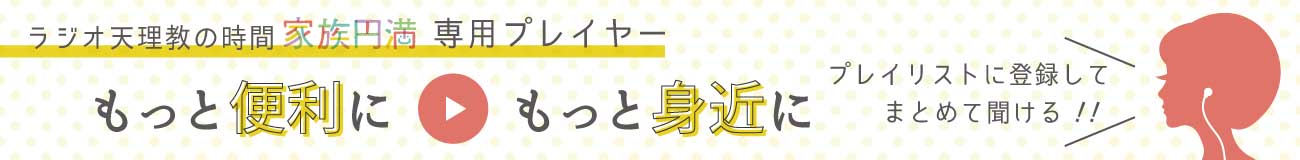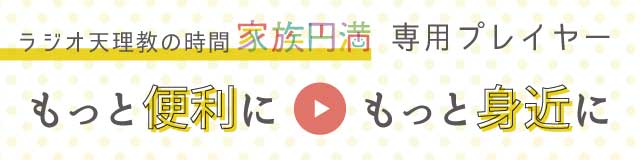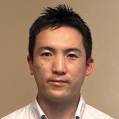第1170回2022年3月19日・20日放送
親と子の関係
昨今問題視される親と子の関係について、教祖の二つのご逸話から思案する。
親と子の関係
親と子の関係をめぐる様々な問題が社会の基盤を揺るがしている昨今ですが、天理教教祖・中山みき様「おやさま」をめぐる逸話には、この問題を考える上で大切なお話がいくつも残されています。
明治十年夏、当時九歳の矢追楢蔵(やおい・ならぞう)さんは、川遊びをしているときに、男性器を蛭にかまれてしまいました。二、三日経つと大きくはれてきて、場所が場所だけに両親も心配して、医者にかかり加持祈祷もするなど、色々と手を尽くしましたが、一向に回復の兆しが見えません。
その頃、近所に教祖の教えを知る者があり、元来信心家であった楢蔵さんの祖母のことさんが、勧められて信仰を始めました。ところが、父親の惣五郎(そうごろう)さんは、信心する者を笑っていたくらいで、まったく相手にしようとしません。ことさんと母親のなかさんが三日ごとに交替で、楢蔵さんを連れてお屋敷へお参りしたのですが、なかなかご守護を頂くことができませんでした。
そんなある日、ことさんは信心の先輩に、「『男の子は、父親付きで』と、お聞かせ下さる。一度、惣五郎さんが連れて詣りなされ」と諭されます。家へ戻ったことさんは、さっそく惣五郎さんにこのことを話し、「ぜひお詣りしておくれ」と頼みます。そこでようやく惣五郎さんは、楢蔵さんを連れて初めておぢばへ帰りました。するとどうでしょう、三日目の朝には、楢蔵さんはすっきりご守護を頂いたのです。
教祖は、楢蔵さんの怪我を通して、父親の惣五郎さんに心の入れ替えを促し、信仰を通して、父親と息子が、さらには家族一同が深く絆を結ぶようにとお諭しくだされたのです。
また、こんなお話もあります。当時十五歳の桝井伊三郎さんは、母親が危篤の容態(ようだい)となり、夜明けに6キロの道のりを歩いて、教祖のもとへおたすけを願い出ました。
「母親の身上(みじょう)の患いを、どうかお救け下さいませ」
すると、教祖は、
「伊三郎さん、せっかくやけれども、身上救からんで」
と仰います。他ならぬ教祖の仰せですから、伊三郎さんは「さようでございますか」と、そのままうちへ戻りました。けれど、苦しんでいる母親の姿を目の当たりにすると、心が変わってきます。
そこで、再び教祖のもとへお願いに行きますと、
「伊三郎さん、気の毒やけれども、救からん」
と。
教祖の仰せだからやむを得ないと、その時は得心するのですが、うちへ戻ると、待っているのは苦しむ母親。どうにもジッとしていられません。伊三郎さんは、三たび6キロの道のりを歩いて教祖のもとを訪ねました。
「ならん中でございましょうが、何んとか、お救け頂きとうございます」
すると、教祖は、
「救からんものを、なんでもと言うて、子供が、親のために運ぶ心、これ真実やがな。真実なら神が受け取る」
と仰せになりました。
その後、母親の病気はすっきりと救けていただき、八十八歳の長寿を全うした、と伝えられています。
「親のために」という、子供の一途な思い。それは、実に美しく尊いものです。神様は、伊三郎さんの母親を思う真実の心を、見定められたのです。
親子の関係の出発点となるのは、神様の私たち人間に対する深い親心です。この二つの逸話も、親と子の関係について思案するようにという神様のメッセージとして、よく味わい、素直に受け取ることが、親子の良い関係を築くきっかけになると思うのです。(終)

 HOME
HOME