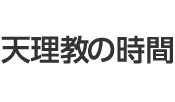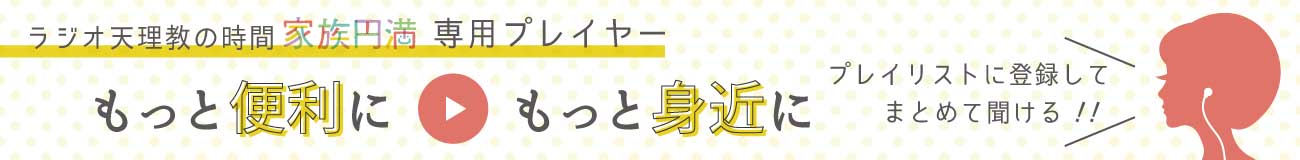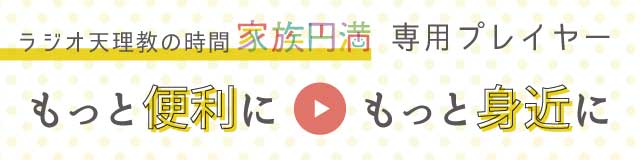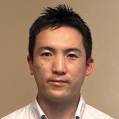第1175回2022年4月23日・24日放送
小さい時から
若い頃、教祖にたすけられ、生涯をご恩報じに捧げた二人の信仰者の逸話をひもとく。
小さい時から
常にあたたかい親心をもって、数多くの人々をたすけられ、導かれた天理教教祖・中山みき様「おやさま」。若い頃に教祖と出会い、そのお慈悲にふれた人々の中には、生涯をかけてご恩報じに励んだ信仰者が数多くいます。
明治十六年、今川聖次郎(いまがわ・せいじろう)さんの長女ヤスさんは、九歳の時、花疥癬という、膿を持つ伝染性の皮膚病にかかりました。ヤスさんが親に連れられておぢばへ帰り、教祖の御前に出させて頂くと、教祖は「こっちへおいで」と仰いました。恐る恐る前に進むと、「もっとこっち、もっとこっち」と仰せられます。
それで、とうとうお膝元まで進ませて頂くと、教祖はお口でご自身の手を湿らせ、そのお手でヤスさんの全身を、「なむてんりわうのみこと」と唱えながら、三回お撫でくだされ、続いてまた三度、また三度とお撫でくださいました。
ヤスさんは子ども心に、身体についた汚れものを少しもおいといなさらない教祖の大きなお慈悲に感激しました。翌朝、起きてみると、花疥癬は跡形もなく治っていたのです。
ヤスさんの教祖の親心に対する感激は、成長するに従ってますます強くなり、そのご恩にお応えさせて頂こうと、生涯、神様の御用の上に励んだのです。(教祖伝逸話篇129「花疥癬のおたすけ」)
また、
明治十二年、十六歳の抽冬鶴松(ぬくとう・つるまつ)さんは、胃の患いから危篤となり、医者も匙を投げてしまう状態でした。親戚筋からの勧めもあり、入信を決意した鶴松さんは、両親に付き添われ、戸板に乗せられて大阪からおよそ五十キロの山坂を乗り越え、ようやくお屋敷へ到着しました。
翌朝、さっそく教祖にお目通りさせていただくと、教祖は、「かわいそうに」と仰せられ、着ていた赤の肌襦袢を脱いで、鶴松さんの頭から着せられました。すると、教祖の肌着の温みを身に感じた鶴松さんは、夜の明けたような心地がしたと言い、あれだけ苦しんだ難病も、やがて全快のご守護を頂いたのです。
鶴松さんは後年、その時のことを思い出しては、「今も尚、その温みが忘れられない」と口癖のように言ったと伝えられています。
二人にとって教祖との出会いは、生涯の行方を決定づけるほどに、心に深く刻まれた出来事だったのです。(教祖伝逸話篇67「かわいそうに」)
教祖は、
「もう道というは、小さい時から心写さにゃならん」(「おさしづ」M33・11・16)
と仰せられ、幼い子どもへ、この道を伝えることの大切さをお諭しくだされています。

 HOME
HOME