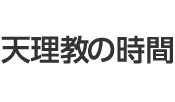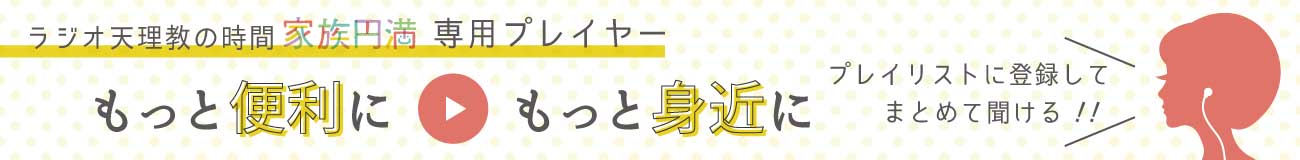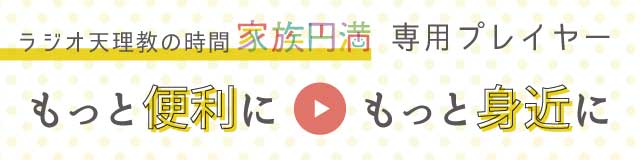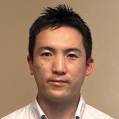第1173回2022年4月9日・10日放送
多様性を認め合う
集団や組織での同調圧力は、個人攻撃や排除の論理を生み出す。それは、陽気ぐらしとは正反対の道である。
多様性を認め合う
人々が同じ場所に集まり、集団で何かを成し遂げる経験は、私たちの成長にとって欠かせないものです。しかし、集団としてのまとまりが強調され過ぎると、皆が同じであることが当然だという〝同調圧力〟が働くことがあるので注意が必要です。
そうした集団においては、一人ひとりの個性が尊重されず、独自の考え方や行動を示す個人が攻撃や排除の対象となり、それがいじめやハラスメントにつながっていきます。
神様のお言葉に、
「人を毀(こぼ)ったり悪く言うてはどうもならん。人を毀って、何ぼ道を神が付けても、毀つから道を無いようにするのやで」(「おさしづ」M23・2・6)
とあります。
「毀つ」とは、「壊す」という意味の古い表現ですが、ここでは人の人格を傷つけたり、排除するといった意味も含まれるでしょう。
また、
「蔭で言う事は十代罪と言う。蔭で言うならその者直ぐに言うてやれ」(「おさしづ」M24・1・29)
「ぼそ/\話はろくな事や無いと思え。誰彼言うやない。そのまゝ直ぐに諭してくれ。こそ/\話は罪を拵える台とも諭し置こう」(「おさしづ」M26・12・6)
ともお示しくださいます。
集団の中には、自分と考えが合わなかったり、疑問に思うような言動を繰り返したりする人もいます。しかし、それをいじめやハラスメントの理由として認めるわけにはいきません。相手に対して疑問に思うことがあれば、そのことを素直に伝えればいいのであって、その人を除け者にしたり陰で悪口を言ったりしても、誰も得をしないでしょう。
誰かに対してある印象を持つと、その印象に当てはまる言動ばかりが目につくようになるものです。私たちはそうやって、「あの人は、やっぱりそういう人だ」と強く思い込んでしまうのです。しかし、それはあくまでその人の一部分であって、日々の生活の中では、こちらの思い込みを覆すような姿も必ずあるはずです。
「この人は、こんな人だ」と決めつけたくなった時には、「この人なりのもっともな理由があるのかもしれない」と、少し間を置いて考えてみてはいかがでしょう。すると、その人に対する印象が変わり、関わり方も徐々に変化していくはずです。時間はかかるかもしれませんが、そうしてそれぞれの多様性を認め合うことが、陽気ぐらしにつながる道ではないかと思うのです。

 HOME
HOME