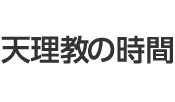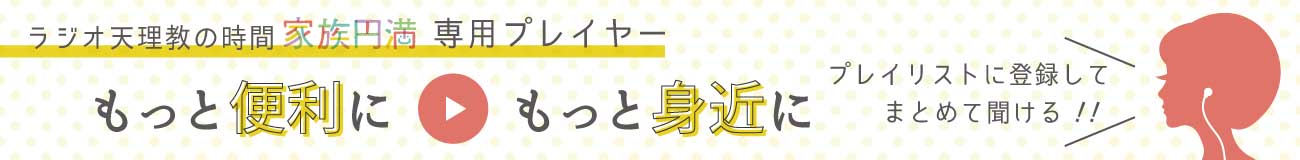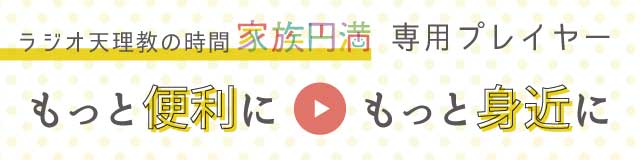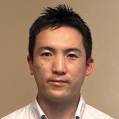第1165回2022年2月12日・13日放送
ふしから芽が出る
「悩み事は、人として成長するための課題である」。心理学のこの考え方は「ふしから芽が出る」という教えに通じる。
ふしから芽が出る
奈良県在住 金山 元春
私は大学で心理学を教えています。また、カウンセリングの仕事にも携わってきました。カウンセリングには、さまざまな悩みを抱えた人が相談にやってきます。
皆さんも、これまでの人生において色々な悩み事を抱えてこられたと思います。そして、それを乗り越えられた時には、人としてひと回り大きく成長できたような実感を得たのではないでしょうか。
そうしたことからも理解できるように、心理学には「人生における悩み事は、私たちを人として成長させてくれる〝課題〟である」という考え方があります。人としての発達を促す課題という意味から、専門用語では「発達課題」といいます。
人生で出合う課題は人それぞれですが、心理学では、ある時期になれば、誰もが取り組む課題があると考えられています。最も有名なのは、青年期における「アイデンティティーの確立」という課題でしょう。アイデンティティーとは、簡単に言うと「自分らしさ」のことです。つまり、青年期の発達課題とは、自分らしさをつかみ取ることです。
皆さんも身に覚えがあると思いますが、青年期の入り口である思春期になると、だいたいの人が親や教師といった大人との関わりを煩わしく感じ、反抗的な態度をとるようになります。心理学では「反抗期」と呼ばれ、それまで当然のように受け入れてきた大人の価値観や世間の常識とされる事柄に疑問や反発を感じ、自分なりの考えが徐々に形作られてくる時期であるとされています。
その過程において、青年は「自分はどんな人間なのか?」「何をして生きていくのか?」「自分にとって大切なもの、価値のあるものは何なのか?」「自分らしい人生とは?」といったことに悩み、迷いながらも、少しずつ自分なりの答えを見出していくのです。このような自問自答を経てつかんだ「自分らしさ」は、その後の人生を支えてくれる軸となります。
このように、青年期の葛藤を一例としてあげるだけでも、人生における悩みとは、ただ苦しいだけの意味のないものではなく、人として成長するために必要なものだと理解できると思います。
そして、こうした理解は、悩み苦しんでいる人のたすけになりたいと願う時にも心得ておきたいことです。これは何も、「その苦しみはあなたが成長するために必要なものなのだから、がんばりなさい!」と教えてあげましょう、という意味ではありません。そのように言われても、苦しみの渦中にある人は、なかなかそうは思えないものです。
私は、「この苦しみにも意味がある」という受け止め方は、相手にぶつけるものではなく、その人のたすけになりたいと願う自分自身の心に治めるものだと思うのです。
人の相談に乗っていると、この先どうしていけば良いのかと不安になったり、先が見えずに希望を失いかけたりする時があります。それでも、希望を失わずにその人を支え続けるためには、自分自身が何かに支えられている必要があります。
何がその支えになるのかは人それぞれでしょうが、私にとって、それは信仰です。
神様のお言葉に、
「さあ/\ふし/\、ふし無くばならん。ふしから芽が出る」(「おさしづ」M22.5.12)
とあります。
また、
「もうあかんかいなあ/\というは、ふしという。精神定めて、しっかり踏ん張りてくれ。踏ん張りて働くは天の理である」(「おさしづ」M37.8.23)
とも教えていただきます。
人生には「もうダメだ」と言いたくなるような悩みや苦しみが生じることがありますが、神様のお言葉からは、そうした悩みや苦しみも、竹の節から芽が出るように、その人の成長にとって欠かせないものだと受け止めることができるのではないでしょうか。
誰かをたすけたいと願う時には、「この悩みや苦しみも、この人にとって意味のあることだ」と信じ、「この節からきっと芽を出すことができる」と希望を持つこと。そうした気持ちで支え続けることができるかどうかが、私たちに問われていると思うのです。
神様は、
「どんな事聞くも一つのふし、見るも一つのふし、さあ/\楽しんでくれるよう」(「おさしづ」M28.7.11)
とも教えられます。
悩み事があっても、「ここから芽を出し、花を咲かせられる」と信じることができれば、その先を確かに楽しむことができると思います。しかしながら、この境地に至るのは簡単なことではありません。不安に押しつぶされてしまいそうになる時もあります。
そんな時には神殿へ行き、神様の前に座り、静かに祈り続けます。すると、「きっと神様にお守りいただける。先案じせずにおもたれすれば良い」という安心感が生まれてきます。何かあっても、神様のもとへ行けば大丈夫。神様が守ってくださるという安心感に、私はいつも守られています。
そして、この安心感を家族や周囲の人へ広げていけるように、「この人も、この子も、神様に守られているのだから大丈夫」との思いで優しく接するよう心がけています。
いつもそのようにいられるわけではありませんが、少しでもそうありたいと祈り続ける日々です。
陽気づくめ
天理教教祖・中山みき様「おやさま」が教えられた「みかぐらうた」に、
いつまでしんゞんしたとても
やうきづくめであるほどに(五下り目 5)
とあります。
陽気づくめの「づくめ」とは、そのことばかりであることを意味します。例えば、「黒づくめの衣装」といえば、衣装が黒ばかりであることを指します。したがって、このお歌は、私たちがいつまで信心したとしても、「常に陽気であり、すべて陽気である」というように、どこまでも明るく勇んだ道すがらを歌ってくださっているように思います。
しかし、実際にそんなことが可能でしょうか。喜べない日も、勇めないこともあるのではないでしょうか。
教祖直筆による「おふでさき」に、
月日にわにんけんはじめかけたのわ
よふきゆさんがみたいゆへから(十四 25)
とあるように、神様は私たち人間が陽気ぐらしをするのを見て、ともに楽しみたいと思召され、この世界と人間をお造りくださいました。
私たちの身体をはじめ、この世の一切のものは、陽気ぐらしのために神様が用意してくださったものです。ですから、この「陽気づくめ」であるはずの世界に、陽気でないものがあるとすれば、それは唯一自由に使うことを許されている、私たち自身の「心」ということになるでしょう。
たとえて言うなら、親が子どもを喜ばせようと、子どもの好きな料理を作り、プレゼントまで買って誕生日会を用意したのに、肝心の子どもが学校で嫌なことがあって機嫌を損ねて帰ってきたら、せっかくの誕生日会も楽しめずに終わってしまうようなものです。
「陽気な心」を意識して通られた先人の一人に、深谷源次郎さんがいます。鍛冶屋を営んでいた源次郎さんは、もともと陽気な性格でしたが、信心の道に入ってからは、ますますどんなことも明るく悟るようになり、陽気づくめの道を通られました。
たとえば、つまずいて額を打ってこぶができた時には、「痛い!」と言った次の瞬間に、「有難や、有難や」と大声で叫んだそうです。頭を打って何がありがたいのかと周りの者が尋ねると、「痛いということを感じさせてもらえるのが有難いのや」と答えたといいます。
晩年は左目の視力が衰え、日が経つにつれて右目も衰えていきました。そんな中、源次郎さんは、「神様のご守護て偉いもんやないか。鍛冶屋していた時に怪我した方が後から悪くなってきたで」と、実に明るく悟っています。
源次郎さんは、かつて鍛冶屋をしていた時に、作業中に真っ赤に焼けた鉄くずが右目に入り、失明しそうになったところを、不思議なおたすけをいただいて信仰に目覚めたのです。その自らの信仰の元一日を振り返り、失明しそうになった右目からではなく、左目から悪くなってきたことを、神様のご守護だと喜んで、人々に陽気に話しているのです。
「陽気づくめ」というのは、どんな困難な中も、神様の親心を陽気に悟っていく歩みの中に、味わえる境地ではないでしょうか。
(終)

 HOME
HOME