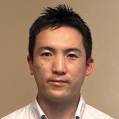第1145回2021年9月25日・26日放送
いちばんの親孝行
教会の住み込みのご婦人が95才で旅立った。40年間共に暮らしてきた彼女との思い出は尽きない。
いちばんの親孝行
大阪府在住 芦田 京子
長年、教会に住み込んでくださっていたご婦人が、95歳で旅立たれた。教会を息子に譲って離れた土地で暮らす私は、コロナ禍のもと、お別れに行くこともままならない。
まだ私の長男が生まれたばかりの頃に出会って、それから40年、共に暮らしてきた。思い出がたくさんあって、夜になると何だか切なくて、眠れない日が続いている。
とんでもない怖がり屋で、歯医者さんにもいけない人だった。初めて会った時には歯があちこちなくなっていたので、「入れ歯を作ろうよ」としつこく誘ったが、なかなか「うん」と言わなかった。しかし、私の押しの強さにあきらめて、やっと歯医者に行って入れ歯を作った。
鼻が詰まって息が苦しいというので、耳鼻科に連れて行こうとすると、嫌だと言う。前に見てもらった時、手術をして鼻の中の異物を取らないとダメだとお医者さんに言われてから、怖くて行っていないという。「手術だけは絶対にイヤだ」と。
その時も私は、ハッタリをかけて「絶対、手術にはならないって、私が保証するから」と、何の根拠もない約束をして、無理やり連れて行った。そうしたらお医者さんが鼻の中を見て、「こりゃ、だめだ」と言って、いきなり麻酔もせずに鼻の中の異物をバチバチ切り始めた。
私は見ていてハラハラしたが、彼女は何をされているのか良く分かっていないものと見え、そのあと息が楽になり、「あなたの言った通り。手術もしないで治ったわ」と喜んでいた。「ね、言った通りでしょう?」と返事をしながら、心の中で、「あれは手術だったのではないか」と未だに思っている。
乙女なところもあり、「初恋の人が忘れられないのよね~」と言っていた。戦争が二人を引き裂いたらしいが、結婚してからも、ご主人の横顔を見ながら「あの人だったらいいのにな~」と、ずっと思っていたという。
何てひどい奥さんだ、とも思えるが、何でも正直に言うところが、何だか憎めなかった。
「えっ、タイプ?そうねえ、わたし、小林稔侍みたいな人が好きなのよ。苦み走った感じがいいわ」と言ったりして、いくつになっても、一緒に恋バナをするのはとても楽しかった。
信仰熱心で、毎日、「おふでさき」という神様のお言葉集を部屋で読んでいた。心に響くものはノートに書き写し、おぼえようとしていた。
子どもさんたちからは大切にされていたが、特にいちばん下の息子さんは、結婚していないこともあって、お母さんが元気でいてくれることが、彼の生きる希望だったと思う。
彼と、高齢になっていくお母さんの行く末について話し合ったことがある。彼は、ほかの兄弟たちには頼りたくないと言っていた。
「みんな、自分の家族のことで精一杯だから、心配かけられないんだ。俺は一人だからさ…」。彼の眼には涙があふれていた。
末っ子だから、本当は兄弟たちにもっと力を貸してもらいたかっただろうし、相談相手にもなって欲しかっただろう。けれど、彼はいつも兄弟をかばって、独り身の自分が母親の世話をするのが一番いいのだと言っていた。
彼にとって、いつしか母親が生きていてくれることが、人生の支えとなっていた。だからこそ、母親が世話になっている教会に足を運び、信仰を受け継いでいったのだろう。
ご婦人が亡くなった後、彼と電話で話をした。苦しみのない、安らかな旅立ちだった、家族やたくさんの人がお別れに来てくれ、さみしいけれど、有難かったと彼は言った。
「きっと、お母さんはあなたのために95歳まで頑張ってくれたんじゃないかな」と言うと、「そうだよね。考えたら、時間がたくさんあったのに、なんだか俺、ボーっと生きてきちゃったな」と言った。
そしてひと息ついて、「おかん、俺も、一緒に連れてってくれないかな」と、ポロっと言って、泣いた。
もっと親孝行できたんじゃないか、もっとお母さんに会いに来るべきだったんじゃないか。そう思っていたのかも知れない。
しかし、兄弟の中でただ一人、母親の信仰を受け継いだのだ。親がいちばん大切にしていたものを守っていくことは、何にも代え難い親孝行ではないだろうか。
「お母さんは、心からあなたのことを喜んでいるよ」
自信を持って私は言った。
「あなたは一人じゃない。教会のみんながいる。みんなで生きていけばいいんだよ。一緒に生きていこう」
そう言って、電話を切った。それが、長い間お世話になったご婦人への、いちばんのはなむけであると信じて。
家族のハーモニー「母の手」
「人間いきいき通信」2020年2月号より
白熊 繁一
母の部屋の窓辺に、季節外れの一輪の白い朝顔が咲いた初秋の日、母の長い人生の幕が降りた。妻や娘夫婦に手を握られ、背中をさすられながら、眠るがごとく、静かで穏やかな最期だった。
その前日、訪問診療の医師から血圧低下の指摘があり、私は母のベッドの横に布団を敷いて寝ることにした。とはいうものの、消え入りそうな小さな息が気になり、母の手を握りながら、その温かさを確かめる長い夜となった。
か細い手を握っていると、さまざまな思い出が心に浮かんでくる。
まだ自宅に冷蔵庫がなかった幼少期、病弱な父が寝込むたびに、母に連れられて氷を買いに行った。話しかけることもできないくらいの急ぎ足で、前だけを向く母の顔。つないだ手からは、緊張が伝わってきた。
小学生のころ、算数の授業が嫌で嫌でたまらず、校庭の芝生で寝転んでいると、学校から家に連絡が入り、母が迎えに来た。さぞかし怒られると思いきや、「お母ちゃんも算数は大っ嫌いや」と大笑いし、手をつないで帰った。母の笑顔のおかげで、授業のエスケープは一度きりとなった。
中学生のとき、クラブ活動中に右腕を骨折した。母は私の左手に箸や鉛筆を持たせ、その手を上から握ってくれた。そして、「どんなに時間がかかってもいい。あなたのペースを大事にしなさい」と言った。
その後、母に手を握られた記憶は思い出せない。
十年前に母が認知症を患い、今度は私が母の手を取りながら歩き、車いすに乗せ、ベッドに寝かせる日が続いた。最近は、私が誰であるのかさえ分からなくなったが、介護する妻や娘夫婦と共に、私も毎朝、母の手と顔を温かいタオルで拭いた。手を拭くたびに、母に育ててもらったありがたさを感じる大切な時間となった。
母が亡くなり、葬儀までの数日、大勢の方々が弔問に来てくださった。ある女性は、冷たくなった母の手を両手で包み、「先生……」と涙を流した。もうはるか昔のことだが、母は当時、子供たちにオルガンを教えていた。そのときの教え子の一人だという。
「先生は絵も上手で、よく教えてもらいました。でも、私が先生から本当に教えてもらったのは〝優しい心〟かもしれません。どんなときも『〇〇ちゃん』と言って、よく手を握ってくれました」と、涙を拭った。
母の一生を振り返ると、若いころは戦争と戦後の混乱期、結婚してからも経済的に不自由な時代が続き、病弱な夫の看病に明け暮れた。きっと一人で泣いた日もあっただろう。でも、私たち子供の前では、小さな喜びに目を向けながら「ありがたい」と口にした。近所の子供たちを集め、特技を生かして心を育んだ。
告別式の日、私の幼い孫や里子がそれぞれに絵を描いて、棺に納めてくれた。孫の絵は、ひいおばあちゃんと手をつないだ姿だった。八十九年の人生の最後まで、常に人の手を握りしめていた母だった。
いよいよお別れのとき、もう一度、母の手にふれた。長きにわたり大勢の人々の心を育ててくれた、ありがたい手、働き者の手、偉大な手だと思った。しっかりと握りしめ、心に刻んだ。
「ありがとうございました。お母さん」
母を見送る日は、長い間居座った秋雨前線が去り、洗いたてのような澄みわたる秋空だった。青空も、白い朝顔も、参列の方々の涙も、何もかもが母の人生を如実に物語っていた。
(終)

 HOME
HOME