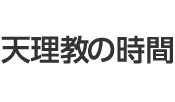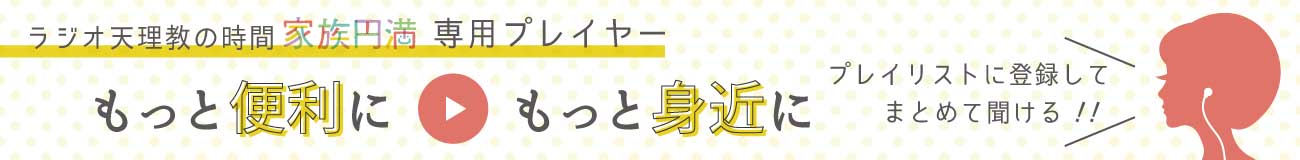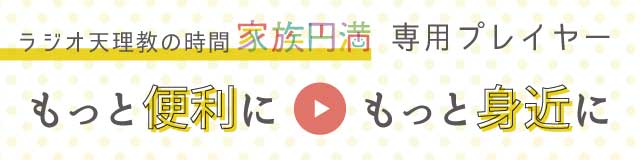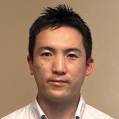第1335回2025年5月23日配信
あっぱれスピーチ
中2の娘が学校のスピーチ大会で登壇した。タイトルは「当たり前と有り難さ」。信仰の角目を堂々と話してくれた。
あっぱれスピーチ
岡山県在住 山﨑 石根
我が家の子どもたちが通う中学校では、毎年3学期になると「私の主張発表会」という行事が開催されます。受験生ではない中1と中2の生徒全員が3分ずつスピーチの原稿を作って、クラスで発表し、みんなで評価をし合う行事です。
発表会の日は参観日も兼ねているので、中2の娘が「お母ちゃん、聞きに来てよ」とお願いをしていましたが、当日、妻は教会の御用があったため、参加が叶いませんでした。ですので、私が「ととは行けるで」と伝えるも、「ととは来なくていい」と、悲しい返事です。
そして迎えた当日、私は都合をつけることが出来たので、学校に足を運びました。他のクラスも覗きましたが、どの生徒たちの発表も目を見張るような素晴らしい内容ばかりです。環境問題や人権問題、SDGsなど大人顔負けのテーマが続き、いよいよ娘の番になりました。
教卓の前に立った彼女は、「当たり前と有り難さ」と元気な声でタイトルを述べると、「皆さんは生きる有り難さを感じたことがありますか? また、それはどんな時ですか? 少し考えてみてください」と、雄弁に語り始めました。
私はタイトルを聞き、「おや?」と思いました。そして、話の内容を聞いていくうちに、「やっぱり!」という気持ちになりました。
それは約一年前の教会の行事で、私が参加した子どもたちに話した「神様の話」そのものだったからです。娘の話には「天理教」とか「神様」という単語は出てこないものの、「当たり前ということはこの世の中に一切ない。当たり前の対義語は〝ありがたい〟だから、日々の当たり前に感謝をして、生きる喜びを感じることが大切だ」というような、私たちが信仰生活で大切にしている内容だったのです。
親のひいき目を抜きにしても、娘の発表は実に圧巻のパフォーマンスであり、日頃から講話を務める教会長の私に勝るとも劣らない、少しも引けをとらない堂々としたスピーチでした。
帰宅後、妻に発表会での様子を伝えた私は、娘に「ととの真似やったなぁ」と少し意地悪を言いました。すると彼女は、「ととの真似じゃないし! 私のオリジナルやし!」と怒ります。
すかさず妻が援護射撃をしてきました。
「いや、考えてみてよ。あなたの原稿を見て、今回のスピーチを考えたわけでもないし、一年も前に聞いた話をこうやって自分の言葉で再現できる、しかも自分の主張に変えられるって、これって考えてみたら、ものすごく立派なことじゃない?」
妻にそう言われ、私も「そうだよな…」と得心しました。
内容は私の影響を受けていたとしても、彼女自身がそれを胸の内に飲み込んで、「こういうことかな?」と消化し、そして「自分の言葉でみんなに伝えたい」と思って、スピーチで表現してくれたのです。そのことを思うと、私は何だかとても嬉しい気持ちになったのでした。
さて、この行事は、発表後に生徒同士で内容や原稿、パフォーマンスの部分をお互いに評価し合い、先生の評価とあわせてクラスの代表を選びます。さらに、その中から学年代表に選ばれると、市が主催する行事に出場できることになるのです。
残念ながら、娘はクラスの代表には選ばれたものの、学年の代表には選ばれませんでした。しかし、彼女が堂々とみんなの前で、私たちの信仰の基本中の基本である「感謝の気持ちの大切さ」を伝えてくれたことが、私たちにとっては大きな大きな喜びであり、金メダルをあげたくなるような雄姿でした。
「育てるで育つ、育てにゃ育たん。肥えを置けば肥えが効く。古き新しきは言わん。真実あれば一つの理がある」(M21・9・24)
という神様のお言葉があります。
私たち夫婦も、子どもを育てる前に、私たち自身が信仰的に育っていくことが大切だと、常々自分たちに言い聞かせているつもりです。素晴らしい神様の御教えや、教祖のぬくもりを何とか子どもたちに伝えたい。そのために私たちがまずこの教えを実践し、その後ろ姿を見て、子どもたちに伝わればと願ってやまない毎日なのです。
その中で、私たち夫婦が唯一「これだけは…」と自信を持って言える信仰実践は、「ありがとう」をたくさん口にしていることでしょうか。未熟な故に失敗や反省の尽きない毎日ですが、おそらくどの家庭にも、またどの夫婦にも負けないぐらい、「ありがとう」「ありがとう」とお互いに言葉にしているかなと自負しています。
もちろん、それなりに夫婦ゲンカもすれば、親子ゲンカもよくします。ですので、思春期を迎えたお年頃の娘は、最近では「ととの理不尽さにいっぱい気づくようになった」と度々指摘するようになってきました。
外でどんなに綺麗ごとや偉そうなことを言っていても、行動が伴っていない私の姿に思う所がたくさんあるのでしょう。
彼女にその矛盾を指摘される度に、神様から問いかけられているような心持ちになり、反省する毎日ではあります。とは言え、それと同じぐらい何かある度に妻にお礼を言い、子どもたちにお礼を言い、そして就寝前も必ずお互いにお礼を言い合うようにしています。
そんな私たちの後ろ姿もまた、彼女には感じる所がきっとあったはずです。なので、私たちは完璧なお手本にはなれていませんが、「当たり前のことは一切ない。毎日の当たり前に〝有り難い〟と感謝して、生きる喜びを味わおう」と友達に主張してくれた彼女の姿が、親として嬉しくて仕方がなかったのです。
長女に、「今回のととの話をパクったこと、『天理教の時間』の話に使っていい?」と尋ねました。すると彼女は、「だ・か・ら、ととの話をパクってないんだってば!」と怒ります。
そうですね。よくよく考えると、これは私の話ではなくて、教祖が教えて下さった教えであり、親神様のご守護のお話です。
私の話が素晴らしいのではなく、娘の話が素晴らしいのでもなく、親神様のご守護、教祖の教えが素晴らしいんだよなぁと改めて実感しました。そのことを一人でも多くの人に知ってもらいたいと、切に願う毎日です。
この家へやって来る者に
「この家へやって来る者に、喜ばさずには一人もかえされん。親のたあには、世界中の人間は皆子供である」(教祖伝3章「みちすがら」)
これは、教祖がこの教えを伝え始められた当初、「貧に落ち切れ」との親神様の思召しのまにまに、食べ物や着る物、金銭に至るまで、次々と困っている人々に施される道中に示されたお言葉です。これこそ、私たち一人ひとりを可愛い我が子と思われ、その帰りを待ちわびておられる真の親のお言葉と言えるでしょう。
さて、人類のふるさと「ぢば」に帰って来た子供たちを、教祖はいかにお迎え下されたのか。具体的に数々の逸話が残されています。
文久三年、辻忠作さんが初めてお屋敷へ帰り、妹のくらさんの気の間違いのおたすけを願い出ると、教祖は、「此所八方の神が治まる処、天理王命と言う。ひだるい所へ飯食べたようにはいかんなれど、日々薄やいで来る程に」と仰せられました。
このぢばは、世界八方をご守護下される親神天理王命様がお鎮まりになる所であり、どんな病も必ずたすけて頂ける。しかし、お腹が減ったからご飯を食べて、さあ元気になった、という訳にはいかない。心迷わずしっかり信心する中に、日々だんだんと薄紙をはぐようにご守護頂ける、とお聞かせ下されたのです。
また、文久四年、山中忠七さんの妻・そのさんが、二年越しの痔の病が悪化して危篤の容態となりました。この時、忠七さんが初めてお屋敷へ帰らせて頂くと、教祖から次のようなお言葉がありました。
「おまえは、神に深きいんねんあるを以て、神が引き寄せたのである程に。病気は案じる事は要らん。直ぐ救けてやる程に。その代わり、おまえは、神の御用を聞かんならんで」(教祖伝逸話篇11「神が引き寄せた」)
親神様が深いいんねんを見定めて、引き寄せたのであるから、病気は心配することはないと、お話し下されています。
教祖は、直筆による「おふでさき」に、
にち/\にをやのしやんとゆうものわ
たすけるもよふばかりをもてる (十四 35)
と記されています。
真実の親の思案というものは、かわいい我が子たちをどのようにたすけようかと、いつもそのことばかりを思っている。誠に親神様の親心は、私たちには計り知れないほど、広く深いものなのです。
(終)

 HOME
HOME