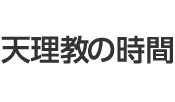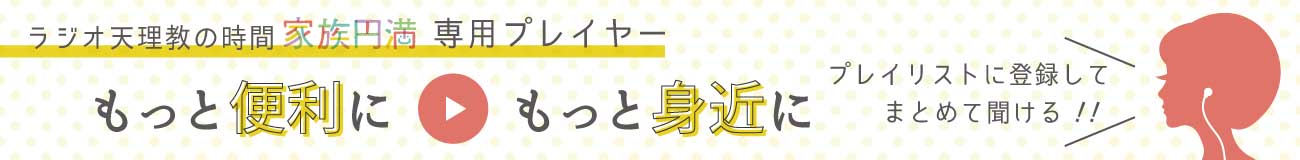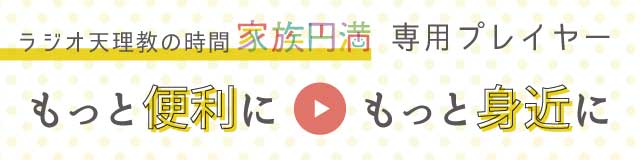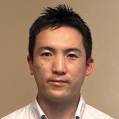第1288回2024年6月28日配信
世界で咲く花
海外からの留学生と共におぢばで学んだ一年間。彼らの伏せ込んだ真実が、やがて世界中で花を咲かせると信じて…。
世界で咲く花
兵庫県在住 旭 和世
私は大学を卒業した後、天理教語学院、通称「TLI」という、海外布教を目指す人が、語学や天理教の教理を学ぶ学校に勤めることになりました。
私の受け持ちの学科は「おやさとふせこみ科」略して「おやふせ」と呼ばれている所で、海外からの留学生が人類のふるさと「おぢば」で教えを学び、真実を伏せ込むという、世界でも唯一無二の学科でした。
まだ20代そこそこだった私は、お世話取りをするどころか、教えてもらうことばかりで、とても新鮮でユニークな毎日でした。
一つのクラスの中で、韓国、台湾、香港、タイ、インド、ブラジル、アメリカなどなど、多国籍の人たちが一堂に会するのですから、色々なことが起こります。
様々な言語が飛び交う中、歌ったり踊ったりの陽気な人や、おおらかでのんびりしている人、日本の文化にはないスキンシップで毎日あいさつしてくれる人、時にはお国対抗で荒々しいケンカが始まったりと、毎日大忙し。でも、そこで教わったことが、今の私の信仰生活の基盤になっています。
「ふせこみ」とは、「欲の心を忘れ、親神様が喜んでくださる真実の種を蒔くこと」であり、いつか必ずその種から芽が出て、花が咲き、一粒万倍となってあらわれてくるのだと教えて頂きます。
学生さんと共に「おやさと」でしっかり伏せ込み、いつかそれぞれの国に帰った時、その「ものだね」から芽が出て花が咲くことを楽しみに、毎日頑張っていました。
その取り組みの一つとして、校舎の裏に畑を作り、農作物を育てることを通して、「ふせこむ」ことの意味を体感できる機会を作りました。農作業は世界共通であり、親神様の火・水・風のご守護をとても身近に感じることができます。
しかし、実際の作業は地味なもので、土を耕し、種をまき、そして毎日毎日、水をやり、草を抜き、追い肥をやり、脇芽をとり、と、作物の丹精にはとても手間がかかるのです。
みんなで汗を流しながらその作業をする時間、いつも決まって私のそばに寄ってくる一人の学生さんがいました。
「せんせ~、なんでこんな事してるんですか~? こんなことやったって意味ないですよ~。もっと大事なことあるでしょう?」
その作業に意味を見出せない彼は、私に向かって不足の言葉をシャワーのように浴びせてくるのです。
最初は私もどうしていいのか分からず、「暑いししんどいけど、頑張りましょう」と、通り一遍の返答しかできなかったのですが、毎回そんな不足の心で作業をしていることは、彼にとってとても勿体ないことに思えてきたのです。
そんな時、教祖・中山みき様「おやさま」のこのようなお言葉を思い出しました。
「どんな辛い事や嫌な事でも、結構と思うてすれば、天に届く理、神様受け取り下さる理は、結構に変えて下さる。なれども、えらい仕事、しんどい仕事を何んぼしても、ああ辛いなあ、ああ嫌やなあ、と、不足々々でしては、天に届く理は不足になるのやで」(教祖伝逸話篇144「天に届く理」)
それからは、彼に「ねえ、もしかしたらくだらないことだと思うかもしれないけど、ここ『おぢば』で頑張ったことは神様がちゃんと見てくださって、あなたがお国に帰った時、きっと大きな芽を出し、花を咲かせてくださる。だから、先を楽しみに今しかできないことを喜んで頑張りましょう」と伝えるようにしました。
他にも、日本語で布教をしたり、神殿の警備をする境内掛のひのきしんや神殿掃除。また、重度の心身障害のある方と一緒に遊んだり、ふれあったりする活動もありました。
そんな、とってもハードで充実した一年間を過ごす中で、学生さんもスタッフである私自身も大きく成長することができました。
さて、あれから20数年が経ち、その時代の記憶も薄らいでいた時、韓国から一本の電話が掛かってきました。
「先生、ぼくです!覚えてますか?」
声を聞いた途端、20数年前の記憶がパッと戻ってきました。不足シャワーの彼です。
「もちろん覚えてるよ!元気にしてるの?」
「はい!とても元気で頑張っています。今度大阪に出張に行くので、先生たちに会いたいです」
さっそく他の先生方とも都合を合わせておぢばで集まることになり、大阪で彼と合流しました。彼専用の運転手付きの高級車でおぢばに向かったのですが、慣れていないこちらは何だか落ち着きません。
彼は自国に帰ると一流企業に入社し、何度かのヘッドハンティングを経て、今では役員の地位にあるとのこと。そんな立派になった彼を見て、「おやふせ」当時の思い出がよみがえりました。
「あの時、最初は草抜きなんて意味ないって言ってたのが懐かしいね。あの一年でコツコツ蒔いた種は、神様がちゃんと見ていてくださったんだね。すごいね」
「ホントに、あの時はよく先生を困らせたね~。日本に出張に来て、おぢばがえりする度に思い出すよ。先生たちにちゃんと恩返ししないとね!今は重要な仕事についていて責任もいっぱいあるけど、がんばってるよ」
「重要な立場になると、いいこともあれば大変なこともあると思うけど、立場が上がれば上がるほど、周りへの感謝を忘れず低い心で通らせてもらってね。神様のご守護は低い所に流れてくるからね」
「先生、それ、いつもおやふせの同級生に言われてるよ!心は低く、高慢になったらダメってね」
卒業しても世界中の仲間たちとつながり続け、神様の望まれる通り方をお互いに求め合い、たすけ合っていることを知り、とても嬉しく思いました。
教祖がお残しくださった「おふでさき号外」に、
にち/\に心つくしたものだねを
神がたしかにうけとりている
しんぢつに神のうけとるものだねわ
いつになりてもくさるめわなし
とあります。
再会した彼をはじめ、当時一緒にがんばった学生さん一人ひとりが伏せこんだ理によって、親里ぢばで蒔かれた種は芽を吹き、生き生きと成長し、世界中でたくさんの花を咲かせているに違いないと、今、思いを馳せています。
浅知恵に走らず
信仰によって開かれる神様の世界は、知識として目で見て確かめられる世界よりも、はるかに広く大きいものです。それは神様の物差しによってはかり、判断する世界だからであり、次元が違うと言ったほうがいいかも知れません。次のお歌は、そのことを端的に示しています。
このせかいなにかよろづを一れつに
月日しはいをするとをもゑよ (七 11)
このはなしどふゆう事にをもうかな
これからさきのみちをみていよ (七 12)
どのよふな高い山でも水がつく
たにそこやとてあふなけわない (七 13)
なにもかも月日しはいをするからハ
をふきちいさいゆうでないぞや (七 14)
この人間世界のことは何もかも、神の支配によって成り立っている。神が諭しているこの話を何のことかと思うかもしれないが、これから先、現れてくることをしっかり見ておくように。たとえどんなに高い山であっても水びたしになることもある。必ず谷底のほうへ水が流れるということもない。そのような常識とはかけ離れたことも現れてくるが、何もかもすべて神が支配しているのだから、やれ大きい小さいと、目に見える形に囚われて判断してはならない。
支配という言葉からは、やや権威的な響きが感じられるかも知れませんが、それは世界中の人間をたすけようとされる親神様の断固たるご意思の表れに外なりません。
水は低いところへ流れていくのが私たちの常識です。大きいほうがいいとか、小さいからよくないなどと物事に固執するのも私たちの常です。そのようなこだわりを捨てて、もっと広く深い神様のご守護の世界に目覚めるべきであることを仰せられています。
この信仰について、「道と世界はうらはら」などと言うことがあります。人間の浅知恵に走るべきではないことを教えられているのです。
(終)

 HOME
HOME