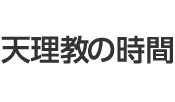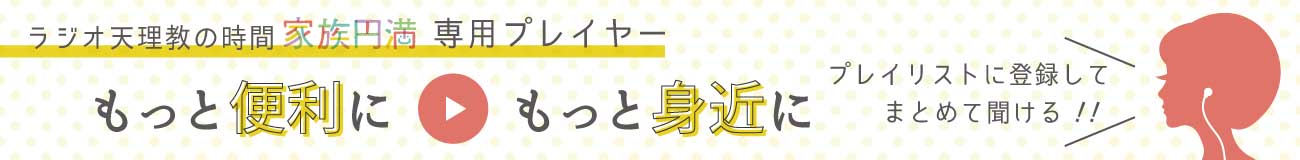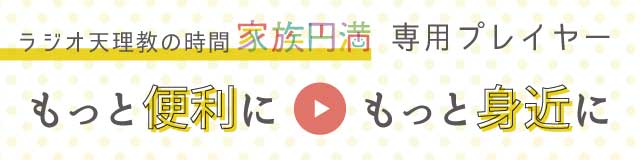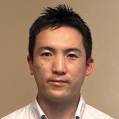第1362回2025年11月28日配信
たすけてもらう力
障害のある人たちの「生きる力を育む」こと。それは「たすけてもらう力を育む」ことでもある。
たすけてもらう力
埼玉県在住 関根 健一
ある日の朝、テレビの情報番組で「受援力」というテーマを特集していました。
援助を受ける力と書いて「受援力」。地震大国と言われる日本ですが、その名の通り阪神・淡路大震災以降、全国各地で数年おきに大規模災害が起こっていて、そのたびに支援の仕組みが見直されてきました。受援力とは、そんな背景の中で注目され始めたキーワードだそうです。
災害対策の取り組みの中で「自助、共助、公助」という考え方があります。東日本大震災のように広範囲で大規模な災害が発生した時、いくら準備をしていたとしても、行政の支援である「公助」はすぐには機能しないことが多いのです。
ですから、まずは自分の力で自分の身の安全を確保するための「自助」。次に、行政の支援が届くまで身近な人とたすけ合う「共助」という考え方を元に、万が一の時に備えておくことが一般的になってきました。
そうした流れの中で、共助、公助を行う際には、誰にどんな支援が必要なのかを把握することが必要になりますが、実際は自分の困った状況を伝えられない人がたくさんいるという現状に直面するそうです。
「たすけてください」「こんなことで困っています」。言葉にすると簡単に言えそうですが、命からがらたすかった後の極限状態では、混乱しているのは当然です。しかも周囲にもたくさん困っている人がいる中で、「私より困っている人がいるのに、この程度のことでたすけてとは言えない」と思ってしまうのも無理はありません。
さらにその番組では、「日本人は幼い頃から『人に迷惑をかけないで生きていきなさい』と教育されることも要因の一つではないか?」と投げかけられ、生活保護を受けられるのに受けない人がいることなども、同じような問題ではないかと触れられていました。
テレビを観ながら、娘が通う特別支援学校のPTA会長をしていた頃に依頼され、「障害のある子供たちの『たすけてもらう力』を育む」というテーマで、教育委員会の機関誌に寄稿したことを思い出しました。
その内容は、「一般の小学校で、教育方針に『生きる力を育む』と掲げているのをよく目にします。でも、特別支援学校に通う児童・生徒の中には、食事や排泄など、生きるための必要最低限の行為にも人の手を借りなければならない子供が多いのです。彼ら彼女らが『生きる』には、『たすけてもらう』ことが欠かせないのです。だから、生きる力を育むことは、「たすけてもらう力を育む」こととも言えるのです」
大体こんな感じの内容でした。また、この時に「日本人は幼い頃から『人に迷惑をかけないで生きていきなさい』と教育されること」の弊害について言及したことも覚えています。
発達障害のある人は、あいまいな言葉のニュアンスを読み取ることが苦手です。「何か困ったことがあったら遠慮なく言ってくださいね」と声をかけたとしても、「その〝何か〟が何を指すのか分からない」となってしまうことがあります。
「お腹が空いてますか?」「夜眠れますか?」など、具体的に聞いてくれればイメージ出来るのですが、支援者や相談者が必ずしもそうした配慮をしてくれるとは限りませんし、すべての行為を例に挙げて聞いていくわけにもいきません。
災害時に限らず、障害のある人たちは日常からそうしたコミュニケーションによる弊害を抱えているのです。裏を返せば、障害のある人たちにも理解しやすいように、たすけてもらう力を引き出す問いかけが出来るなら、災害に直面した時にもスムーズなコミュニケーションが期待出来るのだと思います。
その番組を観た日の夕方、夕づとめで「おふでさき」を拝読し終えると、ふと、
にち/\にをやのしやんとゆうものわ
たすけるもよふばかりをもてる (十四 35)
というおうたが浮かびました。テレビで「たすける」「たすけられる」という言葉を耳にしていたせいかもしれません。
私たち天理教の「ようぼく」は、「つとめ」と「さづけ」の実践を通して、親神様のご守護、教祖のお働きを頂くことが使命です。この行いを私たちは「おたすけ」と呼びますが、人間をたすけるのは、あくまでも親神様のご守護であり、私たちようぼくはおたすけの主体ではありません。
言い換えると、私たちようぼくが行うおたすけとは、「親神様にたすけてもらうための手段を伝えることである」とも言えると思います。
敢えておたすけを先ほどの災害の例に重ねるならば、
「自助」は、おつとめやひのきしんを自らつとめること。
「共助」は、教会に運んで教理にふれたり、会長さんのお諭しを聞いたり、信者同士で研鑽を積むこと。
そして、その先に「公助」として親神様のご守護、教祖のお働きがあるのだと思います。
ですから、「たすけるもよふばかりをもてる」と仰る親神様のご守護を頂くために、私たちは自らおつとめやひのきしんに励み、教会に尽くし、運ぶことが大切なのだと、テレビの話題から改めて教えて頂いた気がします。
教祖140年祭のこの旬。「親神様にたすけてもらうための手段」を自ら実践し、広めていけるように心がけたいと思います。
手の使い方
神様が私たち人間にお与え下された身体の働きの中でも、手は特別に優れた器官です。実に器用で重宝で、何でもすることが出来ます。そして、そこに心を込めることで、その仕事がさらに生きてくるというのが肝心な点です。手作り、手当て、手料理、手縫い、手加減などの言葉は、いずれも心を込めて手を使っている姿を表しています。
教祖中山みき様「おやさま」は、幼少の頃から大変手先が器用で、月日のやしろとなられて後、五十歳を過ぎた頃からはお針の師匠をなされ、近所の子供たちに裁縫を教えられました。
明治十六年頃のこと。梶本ひささんは、ある晩、一寸角ほどのきれを縫い合わせて、袋を作ろうと、教祖の手ほどきを受けていました。そうして袋は出来上がったのですが、この袋に通す紐がありません。すると教祖が、「おひさや、あの鉋屑を取っておいで」と仰せられ、器用にそれを三つ組の紐に編んで、袋の口にお通し下さいました。
教祖は、こういう巾着を持って、櫟本の梶本の家へちょいちょいお越しになり、その度に、家の子や近所の子にお菓子を入れて持って来て下さったのです。(教祖伝逸話篇124「鉋屑の紐」)
また、そのように器用に手先を使われることは、監獄署に拘留されている時でも変わることなく、不要な紙を差し入れてもらってコヨリを作り、それで一升瓶を入れる網袋をお作りになりました。
そして、お供の者にそれをお渡しになり、「物は大切にしなされや。生かして使いなされや。すべてが、神様からのお与えものやで。さあ、家の宝にしときなされ」と仰せられました。(教祖伝逸話篇138「物は大切に」)
どれだけ手に心を込めているかは、ほんのちょっとした動作にも表れるものです。教祖は、お屋敷にいる者に糸紡ぎの用事を出した時、その出来上がったものを三度押し戴かれるなど、そのお手はいつでも心と共にありました。
そして、よろづたすけの手立てとして教えられた「おつとめ」の手振りに関しては、しっかりと手に心を込めるように、特に厳しくお諭し下されています。
「つとめに、手がぐにゃぐにゃするのは、心がぐにゃぐにゃしているからや。一つ手の振り方間違ても、宜敷ない。このつとめで命の切換するのや。大切なつとめやで」(教祖伝 第五章 たすけづとめ)
普段からいかに心を込めて、大事に手を使わせて頂いているか。それが、「命の切換」とまで言われるおつとめのつとめ方にも、大いに関わってくると言えるのではないでしょうか。
(終)

 HOME
HOME