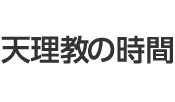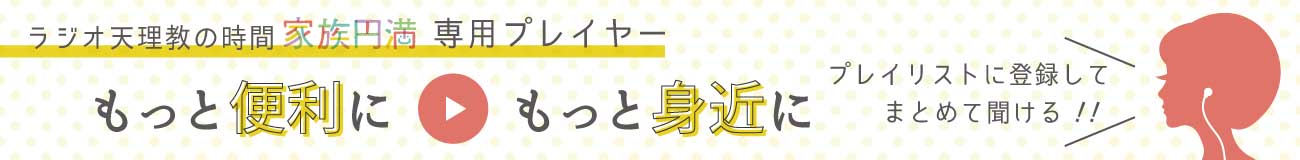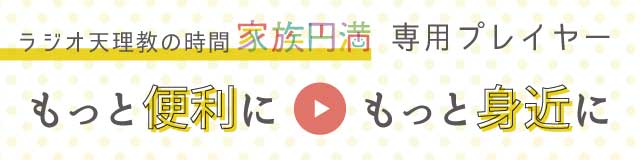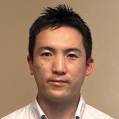第1330回2025年4月18日配信
親より深い愛情
精神を病んだ父親、暴言暴力を振るう母親。二人の子供を連れた一家四人が教会の門をくぐった。
親より深い愛情
岐阜県在住 伊藤 教江
親より深い愛情はない。しかし、親より深い愛情もある……親は子供を深い愛情で育て、子供はその愛情を受けて育って行くものだと信じています。しかし、そんな私の認識が揺らぐような出来事がありました。
当時、ある夫婦は二人の子供に恵まれ、新しく家も建て、家族4人で幸せに暮らしていました。しかし、いつ頃からかだんだんと、母親の喜怒哀楽の感情の起伏が激しくなり、家事も一切しなくなり、暴言・暴力が増えていきました。
そのため父親は、仕事はおろか慣れない家事もままならず、母親の暴力から子供たちを守るのに必死で、遂には疲れ果てて精神を病んでしまいました。そして家族4人は、教会長である主人に付き添われて、教会の門をくぐったのでした。
まだまだ親の愛情の必要な13歳の姉と9歳の弟の生活は、ゴミがあふれ足の踏み場もない家の中で、掃除・洗濯などはもちろん、どこでどう寝ていたのか、一体今日まで何を食べてきたのか、いつの残り湯かわからない泥水のようなお風呂にどう入っていたのか…。想像をするだけで涙がこぼれました。
子供たちは学校でも「気持ち悪い、臭い」といじめにあい、水をかけられたこともありました。それを知ってか知らずか、母親の暴言・暴力はますます酷くなっていき、姉のA子ちゃんは母親の罵声を浴びながら何度も馬乗りになられ、首を絞められたのでした。さらには心を病み、生きる気力を失った父親からも、「一緒に命を絶とう」と、二度にわたり無理やり海へ連れて行かれたこともありました。
A子ちゃんは、そんな自分自身も辛く苦しい中、小さくて病弱な弟を必死で守ってきました。この子供たちは、主人と出会う前には泣くに泣けない、誰にもたすけを求められない、まさに地獄のどん底にいたのでした。
教会ではまず、この家族に温かいご飯をたくさん食べてもらい、私はA子ちゃんと一緒にお風呂に入りました。するとA子ちゃんは自ら「背中を流します!」と言って、私の背中を洗いながら懸命に気を使ってくるのです。
私は驚きました。「まだ13歳なのに…もっと甘えてもいいのに…」A子ちゃんから出る言葉や態度からは、「家には帰りたくない。たすけて欲しい」との思いが痛いほど伝わってきました。
家族4人は、その日から慣れない教会生活が始まりました。2人の子供は学校も転入することになりましたが、A子ちゃんは特に学校生活に辛い経験があり、登校することにとても不安を抱えていました。
幸いにも、A子ちゃんはうちの娘と同じ歳でしたので、娘と同じクラスにしてもらい、娘には「登校から下校までずっと、一緒にそばについて心寄り添って欲しい…」と頼みました。
一方、母親には主人が付き添い、幾つもの病院を回りながら検査を重ねた結果、脳が委縮していく「ピック病」と診断され、入院することになりました。父親は、妻の病名も分かり入院してくれたのでホッとしたのか、「もう教会にはいたくない。家へ帰りたい」と言うようになりました。
父親が家に帰ると言い出したその時、A子ちゃんは弟を連れて、私の前で突然、きちんと正座をして、手をついて頭を畳にこすりつけるようにしてこう言いました。「お願いです。私たちはこの教会に置いて下さい。お父さんと家には帰りたくないです。どうかお願いします…お願いします!」
その子供たちの姿を目の前にした時、私の中にあった「親と子」という認識が大きく揺らいだのです。私は「親」というのは、子供可愛い一条で、自分は寝なくても食べなくても子供のために尽くすのが親である。そして「子供」から「親」を見た時に、わけがあって愛情を持って育ててもらえなくても、子供は親のそばにいたいものであり、親のそばにいることが一番幸せなことであると信じていました。
しかし、この2人の子供の姿は、そうではなかったのです。子供は親以上に自分を大切に育ててくれる人のそばにいることを望んでいるのだと痛感しました。
その後、父親は2人の子供をおいて家へ帰っていきました。子供のことより自分のことを最優先にしていったのです。残された2人の子供は、何も分からない教会生活の中、「おはようございます」の挨拶から始まり、ご飯の食べ方、お風呂の入り方、ゴミはゴミ箱に捨てることなどを教わりながら、大勢の教会の人たちの愛情に抱えられ、教会の家族として穏やかに育てられました。
主人は、この2人の子供の運命を何とかたすけてやりたい、守ってあげたいという親心で抱え続け、我が子同様に、実の親よりも深い愛情で2人の子供を育て上げたのでした。
親よりも深い愛情はない。しかし、親よりも深い愛情もある・・・
教会長である主人から実の親よりも深い愛情で抱きかかえられた子供たちは、親神様・教祖の大きな親心を肌身で感じ取り、報恩感謝の心で日々を通るまで心の成長をしてくれました。私たち夫婦も、たすけ道場・陽気道場の使命を担う教会をお預かりする者として、立派なようぼくへと成長してくれた子供たちの今日に、この上ない喜びを味わう日々です。
「おしい」のほこり
天理教教祖・中山みき様「おやさま」は、私たち人間の間違った心遣い、陽気ぐらしに反する自分中心の心遣いを「ほこり」にたとえてお諭しくださいました。
教祖は、ほこりの心遣いを掃除する手がかりとして、「おしい・ほしい・にくい・かわい・うらみ・はらだち・よく・こうまん」の八つを教えられていますが、そのうちの「おしい」のほこりについて、次のようにお聞かせ下されています。
「おしいとは、心の働き、身の働きを惜しみ、税金など納めるべき物を出し惜しみ、世のため、道のため、人のためにすべき相応の務めを欠き、借りたる物を返すのを惜しみ、嫌な事は人にさせて、自分は楽をしたいという心。すべて、天理に適わぬ出し惜しみ、骨惜しみの心遣いはほこりであります」。
私たちは、心や身体を十分働かせることによって楽しい暮らしができる。そのように、親神様によって造られているのです。心も尽くさず、身も働かせずに横着をしていると、いつしか親神様のご守護を十分に頂けなくなってしまいます。
明治七年のこと。当時十八才の西尾ナラギクさんがお屋敷へやって来て、皆と一緒に教祖の御前に集まっていました。やがて、人々が挨拶をして帰ろうとすると、教祖は娘のこかん様を呼んで、「これおまえ、何か用事がないかいな。この衆等はな、皆、用事出して上げたら、かいると言うてない。何か用事あるかえ」と仰いました。
こかん様が、「沢山用事はございますなれど、遠慮して出しませなんだのや」と答えると、「そんなら、出してお上げ」と教祖が仰せられたので、こかん様は糸紡ぎの用事を出しました。
皆が一生懸命糸を紡ぎ、やがてナラギクさんの所で一つ分出来上がりました。すると教祖がお側に来られ、ナラギクさんの肩をポンと叩いて、その出来たものを三度押し頂かれ、こう仰せられました。
「ナラギクさん、こんな時分には物のほしがる最中であるのに、あんたはまあ、若いのに、神妙に働いて下されますなあ。この屋敷は、用事さえする心なら、何んぼでも用事がありますで。用事さえしていれば、去のと思ても去なれぬ屋敷。せいだい働いて置きなされや。先になったら、難儀しようと思たとて難儀出来んのやで。今、しっかり働いて置きなされや」(教祖伝逸話篇37「神妙に働いて下されますなあ」)
若い時には身体を十分に働かせること。そして、たとえ身体が不自由を抱えても、心をしっかり働かせること。いずれにしても、生涯、働く者として親神様にお使い頂けるのですから、こんなに有難いことはありません。
(終)

 HOME
HOME