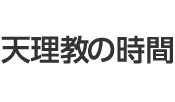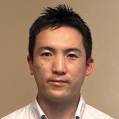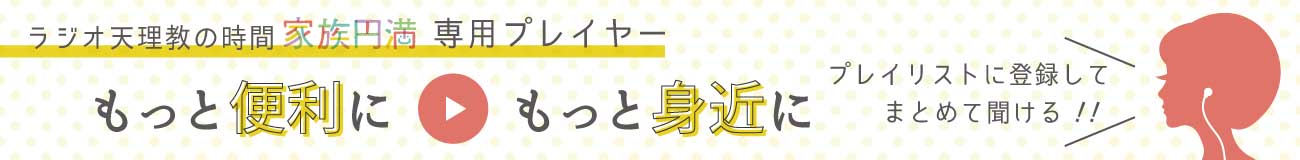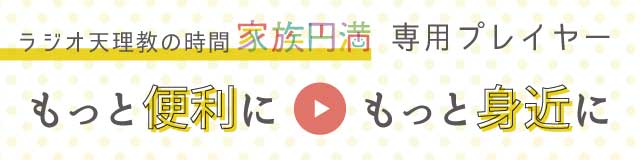第1334回2025年5月16日配信
出直し
20代の頃、80代の男性のおたすけに当たり、「出直し」の教えについて深く考えさせられた。
出直し
千葉県在住 中臺 眞治
今から21年前、私が大学を卒業して間もない頃の話です。ある日の朝、父から電話があり、「Aさんが今、入院していて、いつ出直してもおかしくない病気なんだけど、今日は用があってどうしても行くことが出来ないから、お前、代わりに行っておさづけを取り次いできてくれないか?」と言われました。
Aさんというのは80代の男性で、若い頃から熱心に信仰を続けてきた方です。
それに対して当時の私は、おさづけの理は拝戴していたものの、ほとんど取り次いだことはありませんでした。また、Aさんとは小さい頃に少し面識があっただけで、お話した記憶もほとんどありませんでした。
そういう自分が、病気でもうすぐ出直すかもしれないという人の所に行っていいのだろうか?と迷いましたが、父から「Aさんは昔から熱心に信仰をされてきた方だから。行けば喜んでくれるから」と言われ、「分かりました」とその御用を受けることにしました。
すぐに電車を乗り継ぎ、Aさんの入院している病院へと向かいましたが、道中は緊張でいっぱいでした。死は人間にとって大きな悩み。Aさんは身体的に苦しい中で、精神的にも死と向き合っておられる。今どんな気持ちなのだろうか? どう声をかけたらいいのか?
頭の中ではそのことばかり考えていましたが、結局、答えの分からないまま病室へと入りました。
早速Aさんと目が合いました。長年お会いしていない方だったので、私が誰か分からないだろうと思い、まずは自己紹介と挨拶をしました。すると 「あー眞治君かい。大きくなったね」と私のことを覚えていて下さり、嬉しい気持ちになりました。
そして「ご飯は食べれてますか?」「眠れてますか?」と何気ない会話を始めたのですが、途中からはAさんの方から色々とお話をして下さいました。
30分ほどのお話の中で特に印象に残っているのは、戦後間もない物のない時代の話でした。
「教会につながる者同士で、みんながあったまれる場所を作ろうという話になったんだ。それぞれが貧しい中ではあったけれども、コートを買ったつもり、御馳走を食べたつもりになって、釘やトタン、垂木などの材料を買って持ち寄って、手作りで教会建物を建てたんだよ」と、若い時代に人のたすかりを願って歩まれた日々の事を懐かしそうに語っておられました。
さらに続けて、「僕はね、死ぬのは全然怖くないんだよ。借りた物を返すだけのことでしょ。これから神様の懐に抱かれると思うと、もう嬉しくて嬉しくて仕方ないんだよ」と、本当に嬉しそうな顔で私に聞かせて下さいました。
天理教の原典『おふでさき』では、
このものを四ねんいせんにむかいとり
神がだきしめこれがしよこや (三 109)
と記され、神様によって迎え取られた魂は、そのあたたかい懐に抱かれるのだと教えて下さっています。
また、天理教では死ぬことを「出直し」と言います。死ぬことがこの世で生きることの終わりを意味するのに対して、出直しは、古くなった着物を新しい着物に着替えるように、お借りした身体を神様にお返しし、また新しい身体をお借りして、再びこの世に出直して帰ってくることを意味しています。
教祖・中山みき様は、末女こかん様の出直しに際して、「可愛相に。早く帰っておいで」と優しくねぎらわれました。先ほどのAさんの言葉は、こうした教えを信じ、人にもそう伝えてきたからこそ自然と湧いてきた思いだったのではないでしょうか。
その後のAさんですが、体調の回復にともない退院され、家族の元へと帰っていかれました。そして何度か入退院を繰り返し、数年後に出直されました。
葬儀の日、私はこの時のAさんの言葉を思い起こしながら、Aさんは悔いのない人生を生きたのだなと感じ、自分もそのような人生を生きられたらなと思いました。
この出来事から21年が経ち、今、私がどう考えているのかと言えば、「悔いもないし、いつ出直すことになってもいい」などという気持ちにはなっていません。まだまだ生かしていただきたいと願っています。
しかし、いつかは出直す。その現実は変えようがありませんが、だからこそ、今、生かされていることに感謝しながら、一日一日を大切に過ごしたいものだと考えています。そしていつの日かAさんのように、恐れずに穏やかに、その時を迎えることができたらと願っています。
また、身近な人の出直しを見送る側になった際には、深い悲しみや苦しみに心が覆われてしまい、その克服には長い時間がかかるかもしれません。しかし、信仰がそれらを受け入れるための支えとなり、生きる力を与えてくれるものになると信じています。
一あっての二
この教えでは、物事にふさわしい旬や、順序というものをとても重要な角目としています。旬に合わせて順序良く処すれば、物事はスムーズに運び、万事順調な道を歩ませて頂けるのです。
神様のお言葉に、
「席と言う一あっての二、何程賢うても、晴天の中でも、日々の雨もあれば、旬々の理を聞いてくれ。聞き分けねば一時道とは言わん」(M26・12・16)
とあります。
一があって二がある。二があって一があるのではない。それはいくら賢い者であっても、その順序を覆すことはできません。人間の知恵や考えだけでは、どうにもならないものがあるということです。
私たちの生活の源であるところの自然現象、晴天や雨のご守護、暖かい寒いというのは、人知の支配が及ぶところではありません。また、農作物を育てるには、それぞれの旬に応じて丹精を込めなければなりません。
ある道の先人は、このように語っています。
「考えてみまするに、神様のお恵みの大きいことは、人間心では計り知ることができませぬ。この寒い冬の日に、夏のあの暑い日がどこにあるかと思えましょう。また、夏の日に、この冬がどこにあると思えましょうか。けれども、天然自然の理が巡れば、ここに春夏秋冬の旬というものができて、それぞれに応じてご守護を下さるのであります。
これは、人間の力でどうすることもできません。ただ今、庭を見渡しますると、葉は落ち尽くしており、木の根を分けても、どこにも葉や花の影は見当たりませぬが、時至りて春来たれば、花も咲き、葉も茂り、実も結ぶのであります。
この道は、ただ人間心でこしらえた教えやない、元の神・実の神、親の道でありまして、天に口なし、教祖の口を借りて説いてくれた道でありますから、守らにゃならん、聞かにゃならん、通らにゃならん教えであります。
何ごとも天理に任せてさえおれば、なんにも案じることも心配もいりませぬ。それを、人間心としてどうやらすると、天理に逆らうと、例えば、南風の吹いているのに南に向かって行くようなもの。ゆえに舟が進まぬ。どうやらすると覆ることがあるけれども、南風の時には北へ向かって舟を進めさえすれば、早く港へ舟を着けることができる。天の理とてもそのとおり、理に従って行きさえすれば、苦しみもなく、安全にこの世を渡ることができるのであります。」
(終)

 HOME
HOME