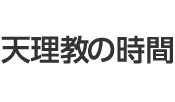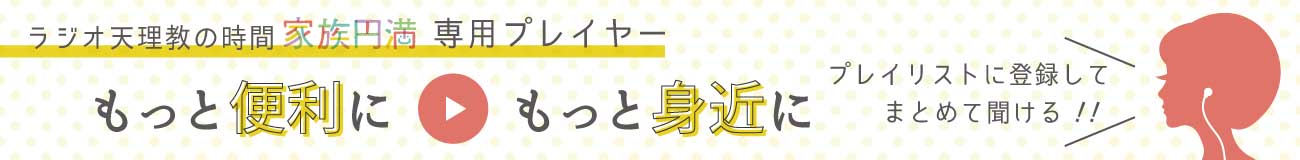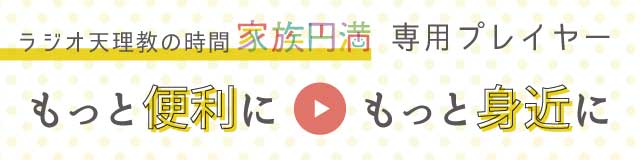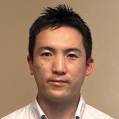第1333回2025年5月9日配信
自分は自分でいいんだと思える子供に
親は子供にとっての「おもちゃ」。反応を見て楽しんでいるのだ。いたずらするのもそのせいかな?
自分は自分でいいんだと思える子供に
静岡県在住 末吉 喜恵
子供が生まれた瞬間は「本当に、無事に生まれてきてくれてありがとう」と心から思うものです。しかし、成長してくるとその思いも段々薄まってきて、もっとこうなって欲しいとか、もっと勉強ができるようになって欲しいとか、親として欲が出てくるのではないでしょうか。
子供にとっては、親が一番最初の「おもちゃ」だと言われています。どうして親がおもちゃなのでしょうか? 実は子供は、親の反応を見て試しているようなのです。
親は自分が泣いたり動いたりすると感情豊かに反応してくれるので、子供からすれば面白いと感じるようです。子供はそんな親の反応が見たくて仕方ないのです。
ハイハイができるようになった頃から、いたずらをすると、親は自分の用事をほったらかしてすぐに対応してくれることを知っていて、その反応が見たくていたずらをしているのだと聞いたことがあります。
三女が3歳で、長男が1歳の時の話です。お絵描きが楽しくなってきた頃で、「まる」をとても上手に書いていました。
ある日、子供たちが外でケラケラ笑って遊んでいました。いつもはケンカもするのに、その日はやけに仲良く遊んでいるなと思っていました。
結構長い時間そのまま放っておいて私は家事をしていたのですが、外に出てみると、何と石を使って車にお絵描きをしていたのです。
我が家の大きなワゴン車の全面、ありとあらゆる場所にお絵描きをして、車は傷だらけになっていました。
私は驚きながらも、「すごく上手にまるや人の顔を描けてるな~。これだけ大きなキャンパスに書いたら、それは楽しかっただろうな~」などと脳天気に思いましたが…そんなこと言っている場合じゃありません!「どうしよう!夫に叱られる!」
そこで、どうやったらそのお絵描きの傷が消えるか考えました。当時いろんなアイデアを紹介しているテレビ番組があり、その中に、「歯磨き粉で簡単に車の傷が消える!」というアイデアを見たことを思い出しました。
子供たちと一緒にきれいに消そう!と、歯磨き粉とタオルを用意しました。思いの外、車がきれいになるので、子供たちも楽しそうに消す作業をしていました。
しかし、案の定この一件を知ったパパは子供たちを思い切り叱りました。子供たちも泣いて謝りました。
「人様の車に同じようなことをしたら、こんなことでは済まされない」「歯磨き粉で消したら、一時はきれいに見えても余計に傷がつく」と、私も子供たちと一緒になって叱られました。確かにそれはその通りだと反省しましたが、今となっては懐かしい思い出です。
その後も子供たちのいたずらは続きました。壁に書いてはいけないということは分かったようですが、押し入れの中だったらバレないとでも思ったのでしょうか? 今度は押し入れの中に入り、またまた絵を描いたのです。それもマジックペンで! でもその時はなぜか「車よりはマシか」と思えるようになっていたから不思議です。
他にも、わざとボールを当てて障子を破ってしまったり、色々といたずらはしていましたが、命の危険が及びそうなこと以外は、大らかに見守ろうと思っていました。そんなにガミガミ怒らなかったのが良かったのでしょうか、そのうちにいたずらはしなくなっていきました。
ついつい、悪いことをしたら叱るということばかり考えてしまいがちですが、子供は親がどうすれば自分に反応してくれるのか? どれぐらい自分のことを見てくれているのか? 内容よりもその反応の大きさであったり強さを求めているのだと思います。
叱ってばかりいると、子供自身の自己肯定感が下がってしまうので、私は子供がいたずらをした時は、それをやめようとしたタイミングで、「ママの言うこと聞いてくれたね、やめようとしてくれたね」と、プラスの言葉をかけていました。
ついマイナスの言葉になってしまいそうな所を、プラスの言葉にしようといつも心がけました。たとえば、走ってはいけない所で走った場合、「走らない!」ではなく「歩こうね」と言ったり、机の上に登ったら「登らない!」ではなく「降りようね」と表現するなど、プラスの言い方に変換する方法はいくらでもあります。
何気ない日常で、やって当たり前だと思えることでも、ちゃんと出来たねと声を掛けることを大切にしてきました。
朝一人で起きてきたら、「ちゃんと時間通りに起きて、身支度も自分でできてるね」と言ったり、「朝ご飯ちゃんと食べたね。元気に食べれるって有難いね」など。普通のことが普通にできること、当たり前のことがどれだけありがたいことなのか、口に出して言うことが大切ではないかと思います。
ちょっと見方や視点を変えることで、至る所に親神様のご守護があることに気がつきます。そこに感動できるかどうか。もっとこうしてくれたらいいのに、と子供に不足をしてしまうこともありますが、生きていること、毎日学校に行くこと、帰ってくることが当たり前ではなく、これほど結構なことはないのです。
私はある時、左足首が腫れてしまい、くるぶしの所にコブのようなものができました。正座もできなくなり、歩き方もぎこちなくなってしまいました。病院で診てもらっても原因は不明でした。
自分の何がいけなかったのかな? 正座した時にゴリっとやってしまったのかな? いけない心遣いをしてしまったのかな?と、その痛いところばかりを気にしてしまっていました。でもある時、その原因を探すのではなく、他のご守護をもっと喜ぼうと思ったのです。
目は老眼っぽくなってきたけど、しっかり見える。耳も聞こえにくくはなってきたけど、しっかり聞くことができる。
ご飯を食べてもしっかり消化されて快便だし、手も指も自由に動かせて仕事もできるし、身体のあらゆる所が健康にご守護頂いていることを感謝するようにしました。
つい、痛いところや辛いところなど、気になるところばかりに目が行きがちですが、そうではなく、もっと視点を大きく持てば、喜びの種は毎日山ほどあります。その喜びの種を探す癖を習慣に出来れば、毎日嬉しいことだらけで、辛いことも辛くなくなるのかなと思っています。
同じように、子供に対しても出来ないところが気になりがちですが、出来ないことに比べれば、出来ていることはもっとたくさんあります。その出来ている所を喜んで、プラスの言葉を掛け続けていきたいと思います。
はらだちのほこり
腹を立てたことがないという人は、おそらくいないでしょう。腹を立てるのに理由などありません。冷静に振り返れば原因をたどることも出来ますが、その場の怒りにまかせ、つい言葉に出してしまうといった経験は、誰しもあると思います。
教祖は、私たちが日常使いがちな、陽気ぐらしに反する心づかいを「ほこり」にたとえて教えられていますが、その中で「はらだち」のほこりについて、次のようにお示しくださいます。
「はらだちとは、腹が立つのは気ままからであります。心が澄まぬからであります。人が悪い事を言ったとて腹を立て、誰がどうしたとて腹を立て、自分の主張を通し、相手の言い分に耳を貸そうとしないから、腹が立つのであります。これからは腹を立てず、天の理を立てるようにするがよろしい。短気や癇癪は、自分の徳を落とすだけでなく、命を損なうことがあります」
教祖は常に、教えを求めて寄り来る人々のそれぞれの心づかいを見極められた上で、お諭し下さいます。
入信後間もない、生来気の短い青年に対しては、「やさしい心になりなされや。人を救けなされや。癖、性分を取りなされや」と仰せられました。
また、夫婦で熱心に信心していた桝井伊三郎さんには、次のようにお話し下さいました。
「内で良くて外で悪い人もあり、内で悪く外で良い人もあるが、腹を立てる、気儘癇癪は悪い。言葉一つが肝心。吐く息引く息一つの加減で内々治まる」
「伊三郎さん、あんたは、外ではなかなかやさしい人付き合いの良い人であるが、我が家にかえって、女房の顔を見てガミガミ腹を立てて叱ることは、これは一番いかんことやで。それだけは、今後決してせんように」
伊三郎さんは、女房が告げ口をしたのだろうか、と疑いましたが、いやいや神様は見抜き見通しであらせられる、と思い返し、「今後は一切腹を立てません」と心を定めたところ、少しも腹が立たなくなったのでした。(教祖伝逸話篇137「言葉一つ」)
神様の教えをほうきとして、日々胸の掃除に努めるうちに、腹立ちの心は消え去ってしまう。実に尊い先人の歩みが示されています。
(終)

 HOME
HOME