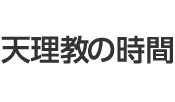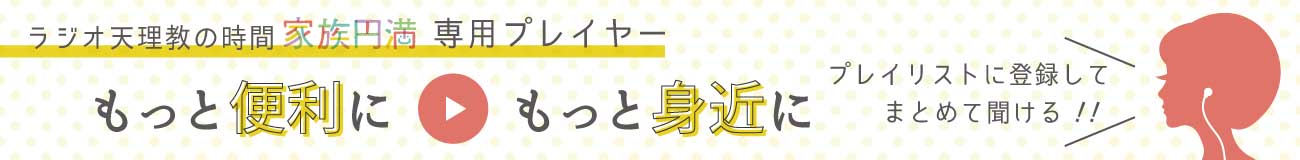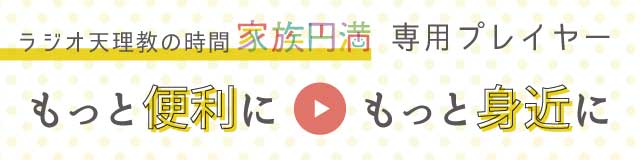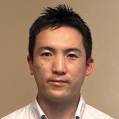第1314回2024年12月27日配信
徳を育む
両親は、小さい頃から徳を育むことの大切さを教えてくれた。それを今、私は子供たちに伝えられているだろうか…。
徳を育む
兵庫県在住 旭 和世
小さい頃、買い物について行って、「お母さんこれ欲しい!」とおねだりすると、母は決まって「そう、これ欲しいの。だけどね、徳まけしちゃうから、また今度にしようね」と言いました。
「ダメよ」とか「我慢しなさい」ではなく、いつも「徳まけ」という言葉が出てきました。幼い私には、「徳まけ」という言葉がどんな意味なのか分かりませんでしたが、「何でも好き放題にすることは良くないんだな、わがまま言ったらダメなんだな」と、何となく感じていました。
なぜそのように母が言っていたのかを理解できたのは、大人になってからのことです。ある時母から、私たちがまだ小さい頃、「子供たちには一切おもちゃを買い与えません」と、神様に心定めをしていたことを聞かされました。
「小さい時に徳を使い果たすと、将来運命が行き詰ってしまう。分からないうちは、親が子供の徳積みをさせてもらわないと!」母はそんな思いで、私たちを育ててくれたそうです。
当時、お友達のいえに行くと、かわいい着せ替え人形やぬいぐるみ、流行りのキャラクターグッズなど、うちにはない色んなおもちゃがあって、とても魅力的でした。それでも、「どうして私は買ってもらえないの?みんなはいいな」などと思ったり、卑屈になったりしたことはありませんでした。母の信念を、子供なりに感じ取っていたからだと思うのです。
また母は、信者さんが普段食べることの出来ない珍しい物を持ってきて下さった時も、神様にお供えし、そのお下がりを必ずいちばんに祖父母に食べてもらっていました。そうして、両親が祖父母をとても大切にしている姿を見て育ったので、おいしい物が目の前をスルーしていっても、うらやましがることもなく、いつも穏やかな気持ちでいることができました。
母は後に、親なら、美味しそうな物を子供たちに食べさせてあげたいと当然思うけれど、それを子供たちの今だけの喜びに終わらせるのではなく、幸せの種にしてあげられたらと思っていたのだと、聞かせてくれました。
天理教教祖・中山みき様のお言葉に、
「お屋敷に居る者は、よいもの食べたい、よいもの着たい、よい家に住みたい、と思うたら、居られん屋敷やで。よいもの食べたい、よいもの着たい、よい家に住みたい、とさえ思わなかったら、何不自由ない屋敷やで。これが、世界の長者屋敷やで」(教祖伝逸話篇78「長者屋敷」)
とあります。
これは、当時のお屋敷に住んでいる人へ向けたお言葉ですが、今を生きる私にとっては、「欲の心、物への執着をなくせば、人は何にもとらわれることなく、何不自由ない幸せに満ちあふれた暮らしができる」という意味に受け取ることができます。それは、小さい頃から、執着の心やとらわれの心を手放すことの大切さを、両親から教えられてきたおかげだと思います。
自分自身の子育てでは、親がしてきてくれたように、我が子に徳を育むことの大切さを伝えられているのか、試行錯誤の日々ですが、この春こんな出来事がありました。
我が家は昨年、長男が天理高校に進学し、今年は長女が天理高校に入学しました。その長女の入学の準備をしていた時でした。
制服や体操服はお下がりを頂けることに決まっていたのですが、カバンだけがなく、買わないといけない状態でした。そんな折、長男から電話があり、「妹のカバンは買わなくていい」と言うのです。「どうして?」と聞くと、驚きの答えが返ってきました。
「去年ボクが高校入った時、お下がりのカバンは嫌だって言って、新しいの買ってもらったやん?」
「ああ、確かにそうやったね」
「だけど、そのあと後悔してな…。物は大切にせなあかんなあと思って、新品使わずに、お下がりのを使ってるねん。だから、新品のカバン、そのまま使わせてあげて!」
「え?そうなん?でも、お下がりのカバン結構傷んでたんちゃう?」
「いいねん、破れるまで使うわ」
まさか、そんなこととは知らず、驚くとともに、とても嬉しく思いました。きっと、学校で、お下がりのカバンを使ったり、物を大切にしているお友達に出会い、教祖のお言葉のように物への執着を手放すことが出来たのではないでしょうか。おぢばでお育て頂いていることを本当にありがたく思いました。
「徳のある人は、巡り合わせがいい」と聞いたことがあります。
巡り合わせには、人の巡り合わせや、時の巡り合わせ、また物の巡り合わせなど色々ありますが、どれも自分ではどうすることも出来ない、神様のお働きだと思うのです。
たとえば、自分で選んで入った学校でも、先生やクラスメイトは選ぶことができません。自分が希望する会社に就職できても、上司や同僚までは選べません。そのような巡り合わせこそ、徳次第だと聞かせてもらいます。ある先生は、徳を育む方法として、三つのことを教えて下さいました。
一つ目は、おつとめで感謝を申し上げ、世界のたすかりを願うこと。
二つ目は、ひのきしんを実行し、自分の時間や身体をお供えすること。
三つ目は、親孝行をして、親や目上の人に喜んでいただくこと。
私はその三つを聞いて、なるほど、徳を育む行いとは、親神様・教祖にお喜び頂ける行いを着実に実行することなのだなと思いました。
それ以来、子供たちにも徳を育むことについて事あるごとに伝えてきたつもりですが、どれだけ理解してくれているかは分かりません。
それでも、子供たちが将来大人になった時に、聞いていて良かったと思ってもらえるよう、まずは自分自身が実行し、子供たちや教会につながる皆さんと共に、「徳」を育んでいきたいと思います。
家族と信仰
天理教では、親から子、子から孫へと代々信仰を伝えていくことの大切さを教えられています。神様は次のようなお言葉で、親と子の関係性についてご教示くださいます。
「人間という、ただ一代切りと思たら、頼り無い。人間一代切りとは必ず思うな。そこで一つ理がある。皆生まれ更わり、出更わりという理聞き分け。親が子となり子が親となり、どんな事もほんになあ、よく似いたるか/\」(M34・9・23)
親と子は生まれ替わりを繰り返す中で、恩の返し合いをする関係としてつながっているのだと教えられます。
教祖・中山みき様「おやさま」をめぐって、こんな逸話が残されています。
明治十年夏、当時九歳の矢追楢蔵さんは、川遊びをしているときに、男性器を蛭にかまれました。二、三日経つと大きくはれてきて、場所が場所だけに両親も心配して、医者にかかり加持祈祷もするなど、色々と手を尽くしましたが、一向に回復の兆しが見えません。
その頃、近所に教祖の教えを知る者があり、元来信心家であった楢蔵さんの祖母のことさんが、勧められて信仰を始めました。ところが、父親の惣五郎さんは、信心する者を笑っていたくらいで、まったく相手にしようとしません。
すると、ことさんは息子の惣五郎さんに対して、「わたしの還暦祝をやめるか、信心するか。どちらかにしてもらいたい」とまで言いました。当時の還暦祝いといえば、近所や親戚中に披露しなければならない大切な行事で、戸主の責任に関わることです。惣五郎さんはその覚悟の上に兜を脱ぎ、ようやく信心するようになりました。
そこで、ことさんが楢蔵さんを連れて教祖にお目にかかったところ、教祖から、
「家のしん、しんのところに悩み。心次第で結構になるで」
とのお言葉がありました。
それからも、ことさんと母親のなかさんが三日ごとに交替で、楢蔵さんを連れてお屋敷へお参りしたのですが、なかなかご守護を頂くことができません。
そんなある日、ことさんは信心の先輩に、「『男の子は、父親付きで』と、お聞かせ下さる。一度、惣五郎さんが連れて詣りなされ」と諭されます。家へ戻ったことさんは、さっそく惣五郎さんにこのことを話し、「ぜひお詣りしておくれ」と頼みます。
そこでようやく惣五郎さんは、楢蔵さんを連れて初めておぢばへ帰りました。するとどうでしょう、三日目の朝には、楢蔵さんはすっきりご守護を頂いたのです。(教祖伝逸話篇 57「男の子は、父親付きで」)
教祖は、「家のしん、しんのところに悩み」とのお言葉で、家族を支える中心として、父親の惣五郎さんに心の入れ替えを促しておられます。息子の楢蔵さんの怪我を通して、信心に励み、父親と息子が、さらには家族一同が深く絆を結ぶようにと、お諭しくだされたのです。
(終)

 HOME
HOME