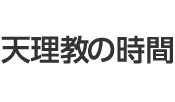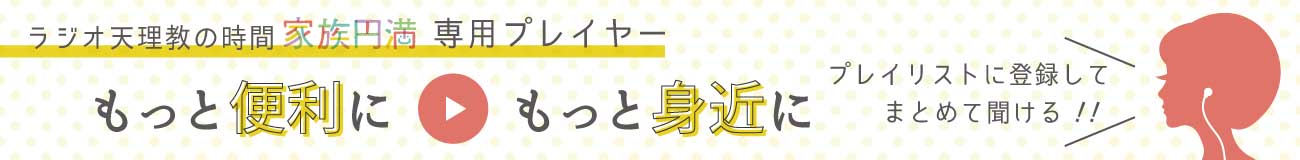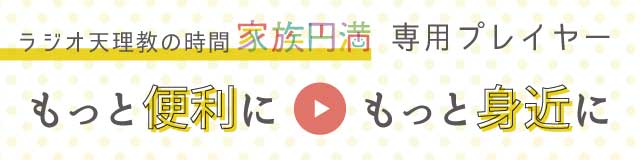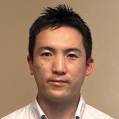第1313回2024年12月20日配信
神様はある?
家出をし、暴力団事務所に出入りし始めたA子さん。親がいくら神様のお話を取り次いでも、全く耳を貸そうとしない。
神様はある?
岐阜県在住 伊藤 教江
「神様なんて絶対にない!お母さんなんて大嫌い!」
当時、高校生だったA子さんは、目に見えない神様は勿論、自分を育ててくれた母親の真心さえも信じられず、問題を起こす度に、母親を怒鳴りつけました。
その後も、A子さんは幾つもの問題を重ね、暴力団事務所に出入りするようになり、ついには家を飛び出してしまいました。その後、A子さんは暴力団の組長と一緒に暮らし始めていたことがわかりました。
それを知ったご両親はどれほど心配をしたことでしょう。早く帰って来て欲しいと連絡をしても、A子さんは会うことを拒否し続けました。そして月日は流れ、いつの間にかA子さんには二人の子供が授かっていました。
いよいよ困り果てたA子さんのご両親は、教会に相談に来られたのでした。さめざめと泣きながら話をするA子さんの母親の姿に、私も同じ娘を持つ親として、もし我が娘が同じような状況に置かれたら…と想像すると、母親の気持ちが、痛いほど伝わってきました。
その日以来、ご両親は娘に帰って来てもらいたい一心で、教会に参拝し、親神様にお願いする日々が続きました。その後、何度も連絡を重ね、私は、やっとA子さんに会えることになりました。
A子さんは、マンション最上階をすべて借りきった暴力団事務所で暮らしていました。私は、そのマンションの駐車場に車をとめ、一人でエレベーターに乗り込みました。
「今から、見たことのない未知の場所へと飛び込んで行くけれど、A子さんは見知らぬ私と会ってくれるのだろうか…?この先、私は一体どうなってしまうのだろう…?」そのうちにエレベーターは最上階に着き、そのドアが開いた瞬間! … 私は、目の前に現れた三匹のドーベルマンに激しく吠えられ、それを聞きつけた大勢の組員に取り囲まれてしまいました。
そこには、映画やドラマでしか見たことのない世界が広がっていました。この光景を目の当たりにした時、私はエレベーターのドアを早く閉めて、すぐに逃げ出したいと思いました。
しかし…その思いとは裏腹に、私の足は前へ前へと勝手に進んでいました。きっと教祖が、私の背中を優しく押して下さったのでしょう。教祖の「救けてやっておくれ…」とのお声が聞こえて来るようでした。
そして、誰とどんな言葉を交わしたのか…記憶がないまま、一番奥の部屋に通され、A子さんと初めて対面したのでした。私はA子さんに「ご両親がどれほど心配し、神様に願い続けていることか…」と話しましたが、「神様や親のことなど眼中にない」と言わんばかりの態度で、目も合わせず全く話にならない状態でした。
そんな中、A子さんのご両親は、毎月おぢばへ帰り、神様のお話を聞く別席を運び続けました。そして早朝から教会に足を運び、ひのきしんをし、おつとめに娘の無事を祈り続ける日々が流れていきました。
すると、A子さんはある日を境に「夫と縁を切り実家に帰りたい」と言うようになりました。ご両親は大変喜びました。しかし喜ぶのも束の間、そう簡単には縁を切らせてもらえない世界であります。親神様にたすけて頂く以外に道はありません。
教会長である主人は、何とかA子さんに救かってもらいたいと、長い年月をかけて、この場では語りつくせない程の真実の限りを尽くしました。その姿を親神様はお受け取り下さったのでしょう、やっとの思いで、A子さんは三歳と二歳の子供を連れて実家に戻ってくる事が出来ました。
早速、私達夫婦はA子さんと三歳の娘さんを連れ、おぢばに帰り別席を運ぶことにしました。その別席の帰りの車中で、私がA子さんに「今日は一日中、下の子をお世話してくれたお母さんにお礼を言いましょうね」と声をかけると「なぜお母さんにお礼を言わなきゃいけないの?」と、そっぽを向きました。
その時です。突然三歳の娘さんが、ぜんそくの発作で苦しみ出したのです。すぐに私はおさづけの取り次ぎをさせて頂こうと「何もわからないだろうけど、手を合わせて親神様、教祖と唱え続けて下さいね」とA子さんに声をかけました。
A子さんにとっては、生まれて初めて見るおさづけに「何?それ… 」と薄ら笑いを浮かべながら手を合わせていましたが、「神様なんて本当にあるの?」とのA子さんの心の声が聞こえてくるようでした。
その後もA子さんは毎月一度、別席を運び続けましたが、その帰りの車中で、必ず三歳の娘さんはぜんそくの発作を起こし、その度におさづけの取り次ぎをさせて頂きました。
そんなある日、A子さんが神様にお礼がしたいと初めて自ら教会に参拝に来たのです。そしてA子さんは、「実は、この娘は生まれてこの方、毎晩のようにぜんそくの発作があり、薬も効かず、夜も眠れずにいました。しかし、別席の帰りにおさづけを受けたその夜だけは、何故か発作が起きなかったんです。でもまた次の日からぜんそくが続き、またひと月経って別席の帰りにおさづけを受けると、その夜だけ発作が起きないんです」と 、その不思議な出来事が続いたと聞かせてくれました。
「神様なんて絶対ない」と言い続けていたA子さんが「えっ? 神様ってあるの…? 神様はあるかも… 神様はある!」と、おさづけの度に娘がご守護を頂いていく姿から、親神様の姿を心で感じ取って行ったのでした。
教祖ご在世当時、ある人の「神様はありますか?」との問いかけに、教祖は「在るといへばある、ないといへばない。ねがふこゝろの誠から、見えるりやくが神の姿やで」と仰せられました。
私達は目に見えない神様をつかむのは、確かに難しいことかも知れません。「神様はあるか?ないか?」 と頭の中でいくら考えても、答えは出て来ないのかも知れません。だからこそ、わからない中でも、親神様に向かって願わせて頂くことの大切さを感じます。
そのためには、我が心のほこりを払い、おつとめやおさづけに心を込める、また日々に親神様のあふれるご守護を味わい、教祖のお言葉を一つ聞いて一つ実行していく。そうすることで、教祖が仰せられる通りの不思議な御守護の姿をお見せ頂けるのだと思います。
鉋屑の紐
一般に鉋屑とは、材木などを鉋で削ったときに出てくる屑のことで、文字通り、捨てられて燃やされる廃棄物と考えられています。
教祖の逸話篇の中に、「鉋屑の紐」というお話があります。
明治十六年のこと、梶本ひささんは夜ごと、教祖から裁縫を教えて頂いていました。ある夜、一寸角ほどの小さな布の切れ端を縫い合わせて袋を作ることを教えて頂き、それが何とか出来上がったのですが、さて、袋に通す紐がありません。
「どうしようか」と思っていると、教祖が「おひさや、あの鉋屑を取っておいで」と仰せられたので、それを拾ってくると、教祖はさっそく器用に三つ組の紐に編んで、袋の口に通して下さいました。
教祖は、このような巾着を持って、親戚の梶本の家へちょいちょいお越しになりました。その度に、家の子にも近所の子にも、お菓子を袋に入れて持って来て下さいました。
教祖は、捨てられる運命にあった鉋屑や布の切れ端を、使い勝手のいい紐や袋に仕立て上げ、見事に再利用されたのです。「もの」の存在価値と、それらを使い切ることの大切さを、何気ない日常の中でお示し下されています。
また、このような逸話もあります。警察や監獄署に十数度拘留された教祖ですが、そのうち数回は、仲田儀三郎さんがお伴をされました。
教祖は拘留中のある時、差し入れられて不要になった紙でコヨリを作り、それで一升瓶を入れる網袋をお作りになりました。それは実に丈夫に作られた袋で、教祖は、監獄署からお帰りの際、それを儀三郎さんにお与えになり、次のように仰せられました。
「物は大切にしなされや。生かして使いなされや。すべてが、神様からのお与えものやで。さあ、家の宝にしときなされ」。(教祖殿逸話篇138「物は大切に」)
この二つの逸話で示されている「ものを大切に生かして使う」ことは、私たちが日常でお手本とするべき、実に尊い「ひながた」です。教祖の「すべてが、神様からのお与えものやで」とのお言葉が、心に深く刻み込まれます。
(終)

 HOME
HOME