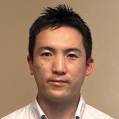第1197回2022年9月24日・25日放送
母が遺した一灯(『日々陽気ぐらし』より)
母の確固たる信仰を横目に、神様と縁遠い生活を送ってきた。定年を迎えた私に、母はさかんに修養科を勧めるが…。
母が遺した一灯
天谷 直純
私は今日この地に在り、後期高齢者となって、妻とともに夫婦二人で暮らしている。生まれてこの方、幾多の人生の変転を経て、老境の歩みに至っている。果たして、この人生は偶然の産物か、あるいは自身の意思によるものか、それとも運命と捉えるべきことなのか―。
長年の疑問が、三カ月間教えを学んだ修養科での経験によって私の腑に落ちた。「身体は神からのかりもの、心のみが自分のもの」。この天理の教えにこそ、人間存在のすべての疑問に対する答えがあることを知るまでに、随分と時間がかかってしまった。
わが家の信仰は母から始まった。戦後間もないころ、父が肺結核を患い、自宅の前にあった教会の会長夫人からにをいが掛かった。たすかりたい一心だったのだろう。父は衰弱した身体を押して、おぢばへ旅立った。しばらくして、会長夫人と一緒に帰ってきた父が、よろけるようにバスから降りてきた光景は、いまでもはっきり思い出すことができる。父は、その半年後に母と二人の幼子を残して亡くなった。
夫の死という悲しみを越えて、母の信仰心は確固たるものになった。教会の月に一度の祭典である月次祭には家族三人で、10キロ余りの山道を徒歩で越え、交通事情が良くなると路線バスを乗り継いで参拝した。これが私の信仰の原風景である。
母は学校給食の職を得て、懸命に働いていた。その母が、折にふれ私たちに説いたのが、33歳で短い人生を終えた、父に見せられたいんねんの道のことであった。この悪いんねんを断ち切らねばならない。母はそう言って、信仰への強い思いを私に伝えた。しかし、少年だった私に、その意味するところを理解できるはずもなく、多感な時代は過ぎていった。
長じては、そのことが心の奥に引っかかっていたのか、身体の調子が悪くなり病院で診察を受けたときなど、結果を知るまで悶々と過ごすことになった。父と同じ運命をたどるのでは、との思いが頭をよぎっていた。しかし「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で、快癒すると信仰のことなど忘れてしまった。
所帯を持ってからは、母の懇願で自宅に神棚を置いてはいたが、朝夕のお参りも疎かにし、ましてや仕事のこともあり、教会参拝も縁遠くなっていた。
故郷に住む母が訪れた際に、神棚に向かって一心にお参りをしているその姿に、自身の不甲斐ない信仰の姿を重ね合わせて、たじろぐばかりだった。
時折、遠方の教会から会長さんが訪ねてこられたときが、わずかばかりの神との対峙の時間となった。
子どもたちの養育も果たし、無事に定年を迎え、第二の人生が始まった。老いた母は盛んに修養科を勧めたが、そのうちに、と言っては母をなだめすかしていた。だが、歳を重ねるごとに、私のなかで修養科への思いは募っていった。
われわれ家族をいつも見守ってくれてきた会長さんのこと、母の思い、そして何よりも、父の生きた年月を遥かに超えた寿命のご守護への感謝。私はとうとう、後期高齢者入り目前にして、おぢばへ向かったのである。
春から暑い夏に向かう、三カ月間の修養には自信がなかったが、ようやくたどり着いた人生の目標点に、母の大きな存在があったことを、しみじみと感じた。母はすでに亡くなっていたが、喜びの想いで遠くから見てくれているであろうことを、修養の糧として通らせていただいた。そして、遅きに失したが、ようやく親孝行の一端を為すことができて安堵した。
しかしある日、詰所の浴槽を掃除していて転倒し、肋骨三本を骨折した。神の御許で、何故このような苦難を受けるのか、痛みに耐えながら悶々と自問自答した。
思い起こせば、私はいくつかの死の危機をくぐり抜けてきた。バイクの事故で道路下へ転落したこと、横断歩道を渡ろうとしたとき、私の顔を擦(かす)るような距離でトラックが走り抜けていったこと―。
そして命永らえて、たどり着いた修養科。ここへ至る道は、神が骨折を通して私に与えた〝目覚めの時〟だったのだ。神の慈愛に満ちた、ぢばの馥郁たる香りに包まれ、気がつくと骨折のことなど忘れて、私は深い幸福感に浸っていた。
親神は、陽気ぐらしをさせて共に喜び合いたいとの思いから人間をお造りくだされたという。陽気ぐらしへの道は、遥かなる遠い道にも思えてくる。ましてや、凡夫たる者においては、わが身思案ばかりが先走り、霧の中の道をさまよい歩いているかのようでもある。
人間とは何か。何故この地で生き、この生活や家族があるのか。それは神の為したことであり、これからの家族の姿も同様なのだ。理屈でも哲学でもない、素直な心で神と向き合う人生。そうした日常から、陽気ぐらしの本筋が、はっきりとした形で見えてくるのであろう。
母が遺した一灯の明かりは、私のなかで大きな光となって煌めいている。いつまでの命かは知る由もないが、神の差配のままに、存分の感謝の心でこれからも通っていきたいと思う。
蔭膳を据える真実の心
学生の頃、たとえば運動会や文化祭などで、なぜか自分への声援だけがよく聞こえてきた、というような経験はないでしょうか。喧噪の中でも必要な声が聞こえるのは、人間の認識がいつも取捨選択されているからだそうです。すべての音が耳に入っても、必要としている情報が無意識のうちに選択され、当人の求める声だけが届いてくるのです。
天理教教祖・中山みき様「おやさま」の、次のような逸話が残されています。
明治の初め頃、教祖の教えは世間に誤解されることが多く、警察からも度々取調べを受けることがありました。
明治十五年、教祖は奈良監獄署へ十二日間拘留されました。その間、梅谷四郎兵衛さんは、お屋敷から監獄署までの十二キロほどの道のりを、毎日差し入れに通いました。
十二日間の拘留を終えて、元気にお屋敷へ戻られた教祖。四郎兵衛さんをお呼びになり、こう仰せられました。
「四郎兵衛さん、御苦労やったなあ。お蔭で、ちっともひもじゅうなかったで」
四郎兵衛さんは不思議に思いました。実は、毎日差し入れを届けてはいたものの、教祖には直に一度もお目にかかることができなかったのです。その上、誰も自分の差し入れのことを申し上げているはずはなく、どうにも合点がいきません。
ところが、そのころ大阪にある四郎兵衛さんの実家では、妻のタネさんが、教祖の御苦労をしのんで、毎日、蔭膳を据えてお給仕をしていたのです。(教祖伝逸話篇106「蔭膳」)
この時、教祖に届いていたのは、蔭膳を据えるタネさんの真実の心でした。これ以外にも、教祖が人々の「真心の御供」を大変喜ばれたという逸話がいくつも残されています。反対に、同じ御供でも「少しぐらいくれてやるか」と、高慢心で持ってきたようなものがあると、たとえそれを召し上がっても、
「要らんのに無理に食べた時のように、一寸も味がない」(教祖伝逸話篇7「真心の御供」)
と仰せられることもありました。
教祖が受け取られる声は、いつでも人の真心であり、真実の行いなのです。
(終)

 HOME
HOME