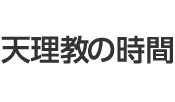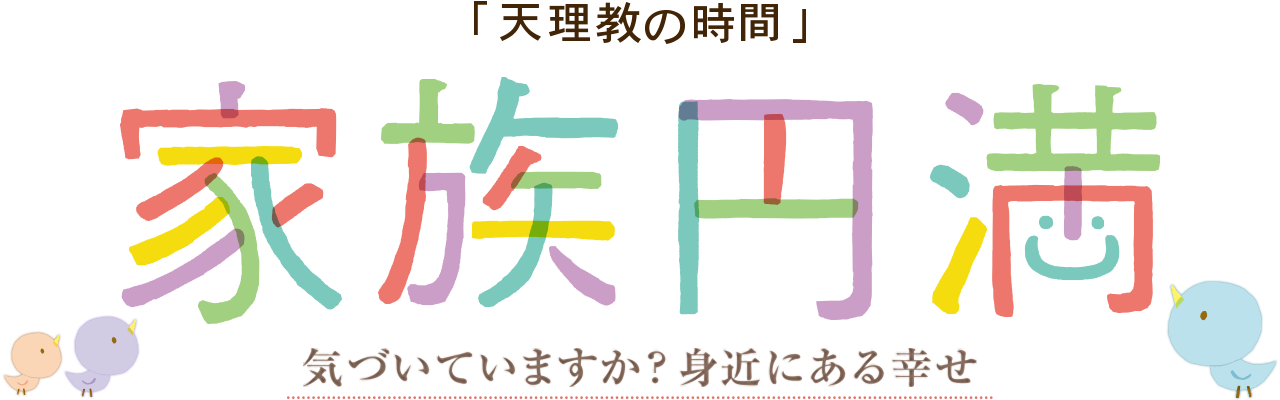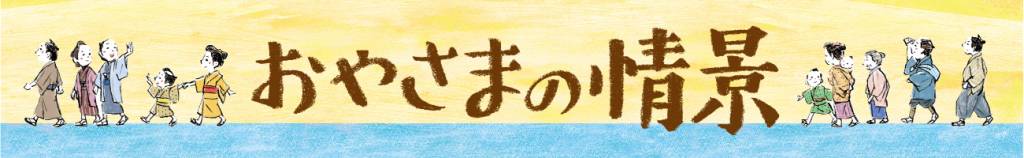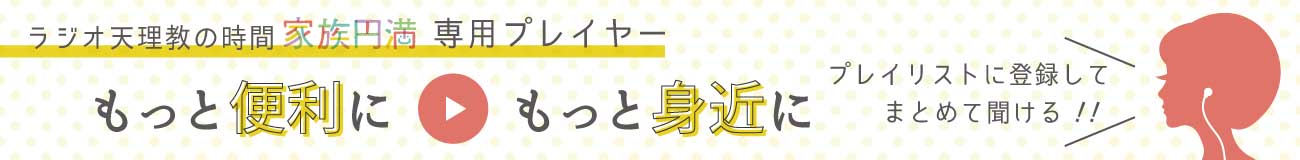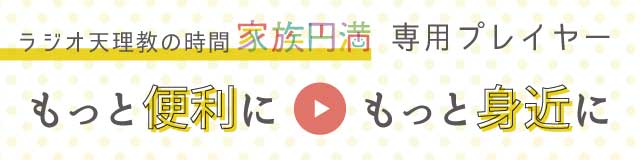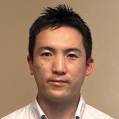地域に「誠」の心を
埼玉県在住 関根 健一
一昨年の春から、地域で「Clean up & Coffee Club」(クリーンアップ・アンド・コーヒークラブ)という新たな活動を始めました。頭文字をとってCCC(シーシーシー)と呼ばれる活動で、コロナ禍になり、人とのつながりが疎遠になってしまったことを憂いた青年が、東京で始めたものです。
活動はシンプルで、簡単に言えば地域のゴミ拾いなのですが、ただ街をきれいにすることだけではなく、地域で友達を作ること、そして地域において「ただ居るだけでいい場」を作ることを目的としています。運営本部は一般社団法人化もしており、やりたいと思った人が気軽に始められるようなサポート体制も出来ていて、今では全国50か所以上で開催されています。
私も東京都内で始まった活動の様子をSNSで知り、ちょうど公民館で行っていた地域交流のイベントがコロナ禍で出来なくなった時期でもあったので、いつか地元でも開催したいと思っていました。
そんな矢先に、知人を通して開催方法や本部担当者への連絡先などを知り、準備を進めることが出来ました。そして、手探りながら地元富士見市の名を冠した、第一回「CCC富士見」の開催に至り、現在、一年半以上続けることが出来ています。
このイベントは親子連れの参加者も多く、子供たちにはいつも助けられています。我れ先にゴミを見つけ、自分の背丈に近い長さのゴミばさみを使い、一生懸命にゴミを拾ってくれる姿は、微笑ましく映ると共に、我々大人たちを勇んだ気持ちにさせてくれます。
そして、ゴミ拾いをしていて気付くのが、タバコの吸い殻の多さです。携帯灰皿が普及して、紙タバコから電子タバコに変える人が増えてきたこともあって、昔ほど落ちてはいないものの、数でいうと他のゴミに比べて圧倒的に多いのが現状です。
CCCの参加者の中には、ほとんど喫煙者がいないこともあり、タバコの吸い殻が落ちていると、「どうしてこんなにタバコの吸い殻が多いんだろう。だからタバコ吸う人って嫌い」と、誰からともなく愚痴がこぼれ始めます。
確かに吸わない人から見れば、タバコは生活に全く必要がないどころか、目の前で吸われれば副流煙が発生し、悪影響さえあるものです。私も昔からタバコが嫌いなので、その気持ちはよく分かります。
そんな会話が耳に入ってきた時に、ふと昔聞いた上級教会の親奥様の言葉が頭の中を過りました。
「教会はね、心のゴミを捨てに来るところなんだよ。でもね、たまにゴミを拾って帰る人がいるの。せっかく教会に運んで来たのに、ゴミを拾って帰っちゃもったいないよね」。
教会でお茶を頂きながら談笑していた時の何気ない一言でしたが、なぜかその言葉が心に残って、今でも一緒に聞いていた妻と時折思い出して話題に上ります。
教会では、おつとめやひのきしんをつとめることで、心の埃を落として帰ります。ですが、たまにせっかく落とした埃を拾うかのように、他人の悪口や不満を垂れ流して帰る人がいるのが残念なんだ、という意味で仰ったのだと記憶しています。
ともすると、周りの人に同調して悪口を言ってしまいそうになる私に、親奥様の言葉がブレーキをかけてくれた気がしました。
私が地元で始めた「CCC」の表向きの目的は、地域に仲間を作ることですが、私自身は心の中で親神様、教祖への感謝を忘れずに「ひのきしん」の精神でゴミ拾いをしています。
自分たちが暮らす街を汚すのは、もちろん褒められた行為ではありませんが、ゴミを捨てた人を責める前に、こうしてゴミを拾えるのも親神様のご守護によって身体が動かせるからであることを実感します。参加者に天理教の教えを具体的に説くわけではありませんが、やがては皆さんに、私の行いを通して「成程」と思ってもらえるように心がけています。
神様のお言葉に、「成程の者成程の人というは、常に誠一つの理で自由という」とあります。
「誠」を辞書で調べると、「言葉や行いに作りごとがない。真実の心」と出てきます。一方、大正時代に宮森与三郎という先人の先生が、「誠」についてこう書き残しています。
「誠というのは、心と口と行いの三つがそろわねば誠やござりません。誠の話するくらいの人は、世界にはささらでかき集めるほどある。口でどれほど誠なことを言うても、誠なことをせなかったら、それは誠ではございません」。
CCCの活動で言えば、ゴミ拾いという行いに、感謝の心が伴っていること、そして言葉で参加者の方たちを勇ませること。そのように、心と口と行いが揃うように実行してこその「誠」である。この活動を通して、今の私に必要なことを教えて下さっていると感じました。
地域の活動の中で、参加者の皆さんに言葉でストレートに伝えることは難しくとも、常に誠の行いを心がけていれば、親神様のご守護の有り難さ、教祖のひながたの素晴らしさが伝わると信じて、この活動を続けていきたいと思います。
だけど有難い「たすかるキーワード」
よく、物事に「ひたむき」に取り組むという言い方をします。「ひたむき」という言葉は、一生懸命、健気に、一途に、真面目になど、そういう意味を含んでいると思います。このことが私は大事だと思います。
子供がひたむきに、一途に、一生懸命、健気に努力している姿は、親神様からご覧になれば、「いじらしい」とお感じになると思うのです。をやが「いじらしい」とお感じになったら、絶対に救いの手が伸びる。たすけてくださる。私は、たすかる元は「いじらしい」と感じていただけるかどうかだと言ってもいいような気がするのです。
私の育ての母・富子は水泳選手でした。母は信仰のうえでは全くの一信者、一ようぼくでしたから、河原町大教会長であった父のところへ嫁ぐときは、ずいぶん不安だったようです。
その母に、長老の役員先生が、こう言ったそうです。
「奥さん、心配せんでよろしい。奥さんが一生懸命つとめているその姿を、神様が『いじらしいな』とお思いになったら、絶対、身は立っていく。一生懸命、健気につとめている姿さえ受け取っていただいたら間違いない」
母は「『なるほど』と思って努力した」という話を聞いたことがあります。私もそれを聞いて、なるほどと思いました。「布教の家」の若者が、人生経験も少なく、おたすけの体験も無いなかで、大きな成果を上げるのも、このいじらしい姿があるからだと思います。
結婚したカップルにも、私はよくこの話をします。いじらしい夫婦になろう。いきなり立派な夫婦になれるわけがない。しかし、教祖から「いじらしい」と思ってもらえるような夫婦にはなれる。「いじらしい」という言葉は、たすかるキーワードだと思います。
(終)

 HOME
HOME